スポンサーリンク
2025年9月、100年以上の歴史を誇る宝塚歌劇団が、公演で「軍歌」を使用したとして大きな騒動に発展しました。
宙組の新トップスター、桜木みなとさんのお披露目公演という祝祭的な舞台で、なぜこのような事態が起こったのでしょうか。
【なぜ炎上?】宝塚歌劇団が公演で軍歌を使用した問題の概要
今回の騒動は、2025年9月13日に宝塚大劇場で初日を迎えた宙組公演、ビートオンステージ『BAYSIDE STAR』で起こりました。
このショーの終盤、トップスターの桜木みなとさんが、黒の燕尾服姿で楽曲「海ゆかば」を独唱したことが発端です。
この選曲に対し、公演直後からSNS上で「なぜこの曲を選んだのか意図が分からない」「誰も止めなかったのか」といった疑問や批判の声が上がり始め、瞬く間に拡散されました。
この事態を受け、宝塚歌劇団は迅速に対応します。初日からわずか11日後の9月24日、公式サイトで「様々なご意見を頂戴していることを受け、当社において熟考を重ねた結果」として、演出の一部変更を正式に発表しました。
具体的には、宝塚大劇場での公演では即日、歌唱を取りやめて楽曲のみの使用とし、11月から始まる東京宝塚劇場での公演では楽曲そのものを完全に差し替えるという、異例の決定を下したのです。
興味深いのは、SNS上の意見を分析した産経新聞社のサービス「emogram」の調査結果です。それによると、この件に関する投稿のうち、否定的な意見はわずか10%で、肯定的な意見が75%を占めていました。
つまり、批判の声は必ずしも多数派ではなかったのです。にもかかわらず劇団が抜本的な変更に踏み切った理由は、たとえ少数でも「軍歌」という極めて繊細なテーマと結びつくことが、幅広い観客に「夢」を届けるブランドイメージを大きく損なうリスクがあると判断したためと考えられます。
これは、批判の「量」よりも「質」を重く見た、現代的な危機管理対応だったと言えるでしょう。
宝塚歌劇団の炎上の理由は?問題となった軍歌「海ゆかば」とは
宝塚歌劇団の公演が炎上した直接的な理由は、使用された楽曲「海ゆかば」が、単なる古い歌ではなく、「軍国主義の象徴」と「戦没者への鎮魂歌」という、非常に複雑で対立する二つの顔を持っているためです。
この歌の持つ多層的な歴史が、人々の間で大きな解釈の違いを生み、激しい論争を引き起こしました。
「海ゆかば」の歌詞の起源は、8世紀に編纂された日本最古の歌集『万葉集』にまで遡ります。奈良時代の歌人である大伴家持さんが詠んだ長歌の一節で、「海で戦うなら水に浸かる屍となり、山で戦うなら草の生える屍となりましょう。
それでも天皇のお側で死ねるのなら後悔はしません」という、天皇への絶対的な忠誠を誓う内容でした。
この古代の詩が全く異なる意味を持つようになったのは、近代に入ってからです。日中戦争が長期化していた1937年、国民の戦意を高める目的でこの詩に荘厳なメロディーが付けられ、楽曲「海ゆかば」が誕生しました。
この歌は「第二の国歌」とまで呼ばれ、特に太平洋戦争中、大本営発表で日本軍部隊の全滅を意味する「玉砕」を伝える際にラジオで流されたことで、多くの国民にとって「死」と直結する、戦争の痛ましい記憶を呼び起こす歌として深く刻み込まれました。
しかし戦後、「海ゆかば」の意味はさらに複雑になります。軍国主義の象徴というイメージが強く残る一方で、その荘厳な曲調から、戦没者を追悼する「鎮魂歌」としても歌われるようになったのです。
現在でも海上自衛隊が儀礼などで演奏しており、公的な鎮魂の歌としての一面も持っています。
今回の公演では、演出家はこの「鎮魂」の意図で選曲した可能性が高いと考えられています。「海ゆかば」が歌われたのは港町・神戸を舞台にした場面であり、この独唱の直後には、阪神・淡路大震災の復興を願う歌「しあわせ運べるように」が使われていました。
この流れから、演出家は「戦争の犠牲者」と「震災の犠牲者」という、神戸が経験した二つの悲劇への追悼の意を表現しようとしたのではないかと推測されています。
しかし、その芸術的な意図は観客に十分伝わらず、「軍歌」という最も強力な記号だけが一人歩きしてしまったことが、今回の炎上の本質的な理由と言えるでしょう。
スポンサーリンク
宝塚歌劇団の軍歌使用に対する批判と楽曲変更までの流れ
宝塚歌劇団が「海ゆかば」の使用を発表してから楽曲変更に至るまで、社会では賛否両論の激しい議論が巻き起こりました。
批判的な意見の核心は、「どのような意図があっても、戦意高揚に使われた歴史を持つ歌を商業エンターテインメントで扱うべきではない」というものでした。この立場の人々にとって、この歌は戦争の悲惨な記憶と切り離せず、その使用は不適切だと感じられました。
一方で、SNS分析が示すように、実際には使用を容認する声も多くありました。「鎮魂歌としての意図を汲むべきだ」という意見や、海上自衛隊でも使用されている事実を挙げて、単純に「軍歌」と断じることへの異議が見られました。
また、「楽曲の変更は過剰反応で、表現の自由を狭めることになりかねない」という、文化と社会の関係性を問う中立的な意見もありました。
議論が深まる中で、演出家である斎藤吉正さんの真意を探る考察も進みました。最も有力視されたのは、やはり「鎮魂のシークエンス」という解釈です。戦争によって失われた命への追悼と、その犠牲の上に現在の平和があることを忘れない、というメッセージが込められていたのではないか、という見方です。
さらに、公演期間中に産経新聞のコラムで評論家の新保裕司さんが「『海ゆかば』を聴き、首を垂れる時間を持つべきではないか」と論じていたことから、演出家がこうした保守的な論調に影響され、歴史の忘却に警鐘を鳴らすという、より積極的な意図を持っていた可能性も指摘されています。
これら一連の出来事の流れは非常にスピーディーでした。9月13日の公演初日を皮切りにSNSで議論が激化し、複数のメディアが報道。社会的な注目が集まる中、宝塚歌劇団はわずか11日後の9月24日に演出の変更を正式に発表し、事態の収拾を図りました。
この迅速な対応は、議論のさらなる拡大によるブランドイメージの毀損を避けるという、危機管理の観点からの経営判断が強く働いたことを示しています。
まとめ:宝塚歌劇団の軍歌問題が投げかけたもの
宝塚歌劇団の『BAYSIDE STAR』における「海ゆかば」の使用問題は、単なる選曲ミスではなく、芸術表現と歴史、そして現代の観客の感受性が複雑に絡み合った、極めて象徴的な出来事でした。
この騒動から明らかになったのは、第一に、「海ゆかば」という楽曲が、現代日本において未だに意味が固定されていない「生きた歴史」の象徴であるという事実です。
ある人には軍国主義の記憶を、別の人には鎮魂の祈りを想起させるこの歌は、意図せずして、日本社会が抱える戦争の記憶を巡る国民的な議論を呼び覚ましました。
第二に、宝塚歌劇団が下した楽曲変更という決断は、大衆に「夢」を届けることを使命とする組織にとって、論争自体がブランド価値を損なうリスクであるという認識に基づく、現実的な選択でした。
芸術的意図を説明して対話を試みるよりも、論争の火種そのものを取り除くことで、ブランドイメージを守る道を選んだのです。
最終的にこの一件は、日本の芸術団体が国の困難な過去に触れる際に、いかに繊細な配慮が求められるかを示す事例となりました。
演出家の芸術的挑戦は、観客とのコミュニケーション不足と、楽曲が持つあまりにも強力な歴史的文脈の前に、意図した形では届きませんでした。
これは、主流のエンターテインメントの世界では、社会の調和が優先されるという現実を浮き彫りにしたと言えるでしょう。
スポンサーリンク






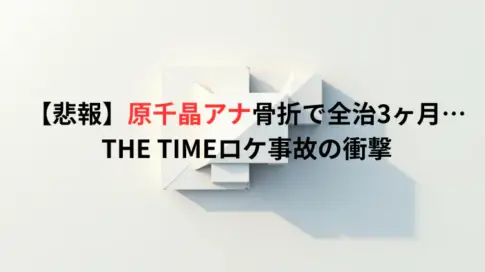


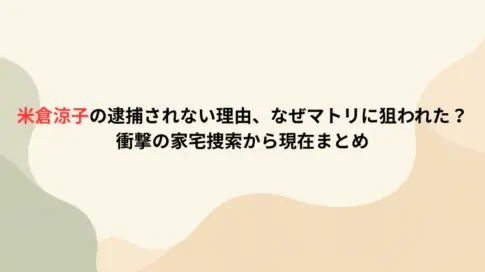




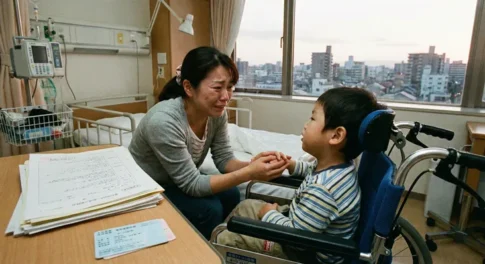







コメントを残す