スポンサーリンク
2024年4月、日本のすべての刑務所で、刑務官が6桁の「識別番号」を制服に表示し、受刑者を「さん付け」で呼ぶという、二つの大きな制度変更が始まりました。
なぜ、これまで匿名だった刑務官を特定できるようにし、呼び方まで変える必要があったのでしょうか。
刑務官の識別番号はなぜ導入された?
刑務官の識別番号が導入された直接的な理由は、名古屋刑務所で起きた職員による受刑者への暴行事件をきっかけに、職員の「匿名性」をなくし、一人ひとりの行動に責任を持たせるためです。
この背景には、目を背けることのできない深刻な問題がありました。2021年から2022年にかけて、名古屋刑務所に勤務していた22人もの刑務官が、複数の受刑者に対して暴行や暴言を繰り返していた事実が発覚したのです。
顔を殴ったり、サンダルで叩いたりするだけでなく、薬を求める訴えを無視するなど、その内容は極めて悪質でした。
この事件で最大の問題点とされたのが、刑務官の「匿名性」でした。
これまで刑務官は、出所者からの報復を防ぐという名目で名札を着けておらず、受刑者から見れば誰が誰だか分からない状態でした。このため、被害を受けても誰から不適切な行為をされたのかを特定できず、正式な訴えを起こすことが非常に困難でした。閉鎖された刑務所という環境と職員の匿名性が、事実上の「やりたい放題」を許す温床となっていたのです。
さらに深刻なのは、これが初めてではなかったという事実です。実は名古屋刑務所では、2001年から2002年にかけても刑務官の暴行で受刑者が死傷する重大事件が起きていました。
この事件を機に法律が改正され、一度は大きな改革が行われたにもかかわらず、約20年後に同じ過ちが繰り返されました。このことは、問題が一部の職員の資質にあるのではなく、組織全体に根付いた構造的な欠陥であることを示しています。
この事態を重く見た法務省は、外部の専門家による「第三者委員会」を設置しました。委員会は徹底的な調査の末、問題は名古屋刑務所に限らず、規律を重視するあまり人権意識が薄れているという全国の施設に共通する「組織風土」にあると結論づけました。
そして、二度と悲劇を繰り返さないための具体的な再発防止策として、職員を特定可能にする「識別票」の導入を強く提言したのです。匿名性の壁を壊し、個々の職員の行動に責任を持たせることが、透明性を確保するための不可欠な第一歩だと結論付けられました。
この一連の経緯と提言については、法務省の公式サイトでも公開されており、外部の専門家で構成された「名古屋刑務所職員による暴行・不適正処遇事案に係る第三者委員会」が詳細な調査と提言を行ったことが明記されています。
以下の動画(テレ朝NEWSの報道)は、刑務官への個別番号振り分けが名古屋刑務所の暴行事件を受けた第三者委員会の提言に基づくものであることを簡潔に伝えています。
識別番号の導入と呼び捨て廃止はいつから?
3月、服装に関する規則を改正する訓令を出し、制服は4月以降に順次更新されました。
刑務官の識別番号の導入と呼び捨ての廃止は、全国の刑務所、少年刑務所、拘置所といったすべての刑事施設で一斉に開始されました。
新制度1:6桁の識別番号とは?
この制度は、全国の刑務所などで勤務するすべての刑務官に対し、一人ひとり異なる6桁の識別番号を割り振り、その番号を制服の右胸にある階級章の上に専用のタグで表示することを義務付けるものです。
これにより、受刑者や他の職員は、いつでもその職員が誰であるかを明確に識別できるようになりました。
この制度の最大の目的は、職員の行動に対する「説明責任」をはっきりさせることです。
誰が行った行為か常に分かる状態にすることで、刑務官自身の規律ある行動を促し、不適切な処遇を未然に防ぐ狙いがあります。
また、万が一問題が起きた場合でも、関与した職員を正確に特定できるため、迅速で公正な調査が可能になります。
新制度2:「呼び捨て廃止」と「さん付け」の目的は?
もう一つの大きな変更点は、受刑者の呼び方です。
これまで一般的だった姓の「呼び捨て」や番号で呼ぶことが廃止され、原則として「さん」または「君」といった敬称を付けて呼ぶことがルール化されました。
これは単なる言葉遣いの変更ではありません。受刑者を一人の人間として尊重し、その尊厳を認めるという、処遇方針の根本的な転換を示すものです。
権力的な上下関係を前提とした一方的な「管理」から、相互の対話を重視する関係への移行を目指す意思の表れでもあります。受刑者に敬意を払うことで、彼らが自尊心を取り戻し、更生への意欲を高める環境を整えることが期待されています。
この二つの改革は、日本の刑務所が目指す方向性を「管理から対話へ」と大きく転換させる、象徴的な意味を持っているのです。
第三者委員会の提言書では、規律秩序を過度に重視する従来の組織風土が問題の背景にあると結論づけており、「さん付け」の導入は、受刑者の尊厳の回復だけでなく、職員の人権意識を改革するための具体的な施策の一つとして提言されたものです。
スポンサーリンク
識別番号制度がもたらす影響は?
識別番号制度は、受刑者にとっては自身の安全と尊厳を守る大きな進歩となる一方、刑務官にとっては責任感が向上する半面、常に監視されているというプレッシャーや報復への恐怖が増大する可能性も秘めています。
受刑者への影響:安全と尊厳の回復
受刑者にとって、識別番号は理不尽な暴力や暴言に対する強力な「盾」となります。自分の行動が記録され、いつでも特定されるという意識は、職員が不適切な行為に及ぶことをためらわせる効果が期待できます。
何か問題が起きた際に「誰に何をされたか」を具体的に申告できるため、泣き寝入りせざるを得なかった状況が改善されます。
また、「さん」付けで呼ばれることは、自分が一人の人間として認められているというメッセージとなり、自己肯定感を育み、更生への前向きな意欲を引き出すきっかけとなる可能性があります。
刑務官への影響:プロ意識と過酷な現実
一方で、日々受刑者と向き合う刑務官にとって、この改革は「諸刃の剣」となり得ます。
常に他者から見られているという意識は、職員一人ひとりのプロ意識を高めるかもしれません。
しかし、その背景には過酷な労働環境があります。
第三者委員会の調査では、刑務官が受刑者との人間関係から非常に強いストレスを感じていることや、職場内でミスが許されず、問題を相談しにくい「心理的安全性の低い」環境であることが明らかになりました。
実際の提言書に添付された職員アンケート結果では、名古屋刑務所の職員が「仕事上の最大のストレス原因は被収容者との関係である」と回答した割合が他施設の平均を大きく上回っていたほか、「自由に意見を言いにくい職場環境」であった実態も指摘されています。
さらに、約8割の職員が「仕事の困難さが社会に理解されていない」と感じ、誇りを持てずにいる実態も報告されています。
このような状況下で、識別番号は不正の抑止力となる一方で、常に監視されるプレッシャーや出所者からの報復への恐怖を増大させる要因にもなりかねません。
真の改革のためには、受刑者の人権を守る取り組みと同時に、刑務官の労働環境や精神的な負担を改善し、彼らが誇りを持って職務を全うできる支援体制を整えることが不可欠です。
【まとめ】
名古屋刑務所で起きた深刻な人権侵害事件をきっかけに導入された、刑務官の「識別番号」と受刑者への「さん付け」。
この改革は、日本の刑事施設のあり方を「罰を与える場所」から「立ち直りを支援する場所」へと大きく転換させるための、重要な一歩です。
匿名性という壁を取り払い、透明性を確保する識別番号。そして、相手への敬意を示す「さん付け」。
これらは、受刑者の尊厳を守り、更生を促す環境を作る上で、必要かつ評価されるべき措置と言えます。
しかし、制度を変えるだけでは十分ではありません。この改革を実質的なものにするためには、長年続いてきた刑務所の組織風土そのものを変革していく必要があります。
また同時に、受刑者の権利を守るだけでなく、日々厳しい環境で働く刑務官たちの精神的負担や孤立にも目を向け、彼らを支える仕組みを構築することが不可欠です。
刑務所を、真に人間的な社会復帰を促す場所へと変えていく道のりは、まだ始まったばかりです。
この「静かなる革命」が、一過性のものに終わらないよう、私たちの社会が継続的に関心を寄せていくことが求められています。
スポンサーリンク




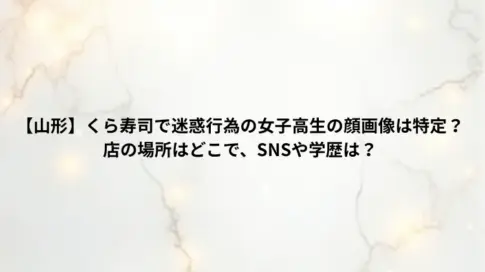


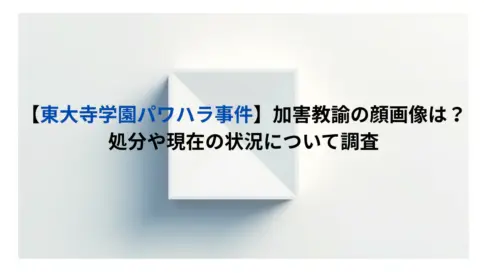
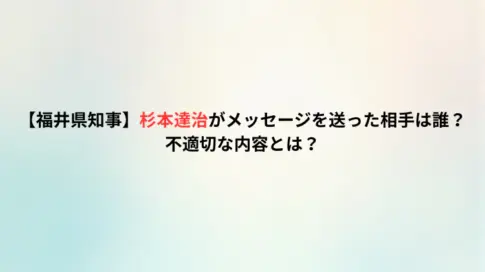

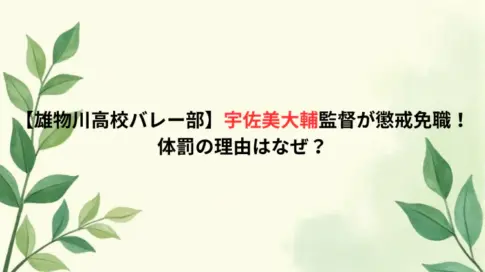
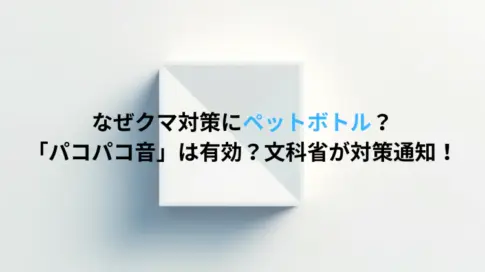



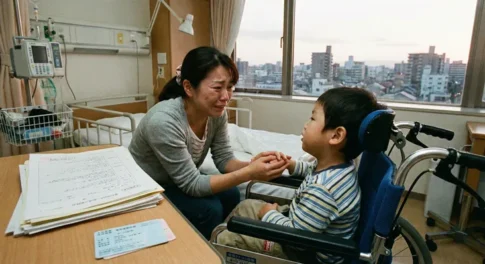







コメントを残す