スポンサーリンク
Number_i 歌詞炎上の理由はなぜ?ポカホンタス問題とTOBE回答まとめ
人気グループ「Number_i」が、その楽曲の歌詞をめぐって大きな物議を醸しています。
11月1日に放送されたNHKの音楽番組をきっかけに、特定の楽曲のフレーズが「差別的表現にあたるのではないか」として、SNS上で急速に拡散され、炎上状態となりました。
Number_iはアメリカでの音楽フェスティバルに出演するなど、海外進出を本格化させている最中でもあり、今回の問題は国内外で大きな波紋を呼んでいるようです。
この記事では、「Number_iの歌詞炎上」問題について、炎上の理由となった具体的な歌詞、なぜその言葉が差別的とされるのか、そして所属事務所である「TOBE」の公式回答まで、現在報じられている情報を整理し、掘り下げていきます。
Number_iの歌詞炎上「ポカホンタス問題」の概要
今回の騒動の発端は、2024年11月1日に放送されたNHKの特別番組『Venue 101 Presents Number_i THE LiVE』でした。 この番組は、Number_iがスタジオに観客を招き、7曲を披露する特別なライブ構成だったようです。
物議を醸したのは、9月にリリースされたアルバム『No.II』の収録曲「幸せいっぱい腹一杯」という楽曲です。 この曲はメンバーの平野紫耀さんがプロデュースを手掛け、「幸せ」をテーマにした明るいメロディーが特徴的な作品とのことです。
番組では、メンバーの歌唱に続いて観客が「ぱい」と連呼するコールアンドレスポンスの場面もあり、Number_iとファンが一体となって盛り上がる様子が放送されました。
しかし、この明るいメロディーとファンとの一体感が、逆に問題となった単語の持つ深刻な歴史的背景との間に強い不協和音を生み出し、問題を際立たせる結果となったようです。
放送直後から、SNS上ではこの曲の歌詞に対する厳しい声が聞かれ始めました。
具体的には、《ポカホンタスをこの文脈で持ってくるの大変にマズい》といった困惑や、《絶対これポカホンタスの歴史を知らずにアンポンタン的な意味の言葉だと捉えて使ってるでしょ》といった、歴史的背景の無理解を指摘する意見が噴出したのです。
加えて、《誰が歌詞書いてGOサイン出したんだろ、すごいな》というように、アーティスト本人たちだけでなく、制作陣やスタッフのチェック体制を疑問視する声も上がっています。
この楽曲の作詞クレジットには、「Pecori」さんと並んで「Number_i」自身も名を連ねていることが確認されており、この点も批判を直接的なものにしている側面があるのかもしれません。
スポンサーリンク
炎上の理由はどの曲?問題となった「ポカホンタス」の歌詞
今回の「Number_i 歌詞 炎上」の直接的な理由は、どの曲のどの部分だったのでしょうか。
炎上の直接的な理由
炎上の理由は、楽曲「幸せいっぱい腹一杯」に含まれる《他力本願な思考はポカホンタス》という一節です。
国内の文脈だけで捉えれば、この「ポカホンタス」という言葉は、語感の面白さや、あるいはディズニー映画のイメージからくる「世間知らず」「おめでたい」といった漠然としたニュアンスで使われた可能性が考えられます。
しかし、この「ポカホンタス」という言葉は、特にアメリカの現代政治と歴史的文脈において、非常に重い「人種差別的な揶揄(スラング)」として認識されているのです。
問題視された「ポカホンタス」という言葉
この言葉が差別的な意味合いを強く持つようになった決定的な出来事として、2016年頃から続く、アメリカのドナルド・トランプさんによるエリザベス・ウォーレン上院議員への攻撃が報じられています。
ウォーレンさんが自身にアメリカ先住民(ネイティブ・アメリカン)の血筋があると主張していたことに対し、トランプさんはその主張を「偽り(フェイク)だ」と攻撃するために、ウォーレンさんを「ポカホンタス」というあだ名で繰り返し呼び、公の場で揶揄し続けました。
この一連の騒動により、アメリカ先住民の団体などからは強い抗議が巻き起こったとされています。 そして、「ポカホンタス」という言葉は「先住民の血筋を偽ると主張する人物」または「先住民全体」を嘲笑するための、現代における明確な差別的表現として広く知られることになったようです。
Number_iが意図したかどうかに関わらず、グローバルな文脈において、《他力本願な思考》というネガティブな特性と「ポカホンタス」という単語を結びつけたことは、この最も深刻な差別の文脈を想起させるものとなってしまいました。
なぜ「ポカホンタス」は差別的表現とされるのか?
では、なぜ「ポカホンタス」という名前そのものが、トランプさんの発言以前から、歴史的にデリケートな問題をはらんでいたのでしょうか。
専門家が指摘する歴史的背景
この点について、アメリカ史を研究する関西国際大学の遠藤泰生(やすお)客員教授が、その専門的な見地から歴史的背景を指摘していると報じられています。
遠藤泰生さんによると、ポカホンタスは17世紀に実在したアメリカ先住民女性の名前です。 彼女の本当の名前はマトアカ(Matoaka)であったとも言われています。 当時、イギリスが現在のアメリカ・バージニア州に植民地開拓のために訪れた際、彼女は先住民族ポウハタン族の酋長の娘でした。
ポカホンタスは、その後、英国人入植者の一人であるジョン・ロルフ(John Rolfe-san)さんと結婚します。 このエピソードが後世に語り継がれ、彼女は先住民と入植者が共存した「平和のシンボル」として美化されていきました。 1995年に公開されたディズニー映画『ポカホンタス』も、このロマンチックな逸話に基づいています。
しかし遠藤泰生さんは、この「恋物語」には隠された視点があると指摘しているとのことです。 それは、「“遅れた”先住民を“進んだ”キリスト教文明に誘った入植者の行いを評価する」という、典型的な植民地主義的な視点だといいます。
実際には、ポカホンタスの物語は、入植者による土地の収奪、文化の破壊、そして彼女自身の若すぎる死といった、先住民にとっての悲劇的な歴史と不可分です。 ディズニー映画で描かれたロマンスや彼女の年齢設定も、歴史的な事実とは大きく異なるとされています。
こうした背景から、「ポカホンタス」という言葉を文脈を無視して不用意に使うことは、先住民を「“遅れた”民族」として見下す、差別的な印象を与えることにつながるのです。
遠藤泰生さんが特に問題視するのは、Number_iの歌詞が《他力本願な思考》と《ポカホンタス》の生き方を結びつけてしまった点であると報じられています。
これは、先住民を「自立できない」「依存的(他力本願)」な存在とみなし、だからこそ「進んだ」入植者による「救済」や「教化」が必要だった、という植民地主義の論理を、意図せずなぞってしまう表現です。
「先住民の感情を逆撫でしかねない、注意が必要な」使い方であったと、遠藤泰生さんは結論付けていると伝えられています。
所属事務所TOBE(トゥービー)の公式回答は?
今回の深刻な「歌詞炎上」問題に対し、Number_iの所属事務所である「TOBE(トゥービー)」はどのように対応したのでしょうか。
TOBEの公式見解
報道によれば、「Smart FLASH」編集部がTOBEに対し、問題となった歌詞に含まれる差別的な表現の認識の有無や、NHKでの放送後のSNS上での反応について見解を尋ねたところ、同社の代理人弁護士から回答が寄せられたとのことです。
その回答は、まず「指摘を受けた表現につきまして、特定の人物、民族、文化、ジェンダー等を揶揄し、又は差別する意図をもって使用したものではございません」と、差別的な意図はなかったとする見解を明確に示しました。
続けて、「一方で、その受け取られ方についてさまざまなご意見があることも真摯に受け止めております」と、寄せられた批判や意見を認識していると述べました。
そして最後に、「弊社といたしましては、今後も多様な文化や価値観への配慮を意識しながら、表現のあり方について慎重に検討を重ねてまいります」と、今後の表現活動における姿勢について説明しています。
過去の類似事例との比較
近年、アーティストの表現が歴史的・文化的な配慮不足から思わぬ批判を集めるケースは、Number_iが初めてではありません。 2024年だけでも、日本国内で大きな騒動が複数発生しています。
一つ目は、2024年6月に起きた「Mrs. GREEN APPLE」の事例です。 彼らの新曲「コロンブス」のミュージックビデオ(MV)が公開されると、その内容に批判が殺到しました。
MVでは、コロンブスのような格好をしたメンバーが、類人猿を思わせるキャラクターたちに人力車を引かせたりする描写などが含まれていたようです。これが、コロンブスによる「侵略」や「植民地支配」を肯定しているとして、歴史認識の欠如を厳しく非難されました。 所属レコード会社とアーティストは謝罪し、MVは即日公開停止となりました。
二つ目は、同年10月の「Snow Man」の事例です。 彼らの楽曲「KATANA」のプロモーション映像において、「岡村寧次」という名前が刻まれた「刀」が映し出されました。
この岡村寧次さんという人物は、中国侵略を指揮した日本軍の指揮官の一人とされており、特に中国のファンから強い反発を招いたのです。所属レコード会社は「歴史的事象に対する配慮に欠ける部分があった」として、映像の公開を停止し、日本語と中国語で謝罪する事態となりました。
これらの事例と今回のNumber_iのケースには、共通点と大きな相違点があるようです。 共通点は、グローバルな視点や歴史的文脈への配慮が欠けていた点です。
一方で、Mrs. GREEN APPLEやSnow Manの事例が「映像」に関する演出が問題視されたのに対し、今回のNumber_iのケースはアルバムに収録された楽曲の「歌詞」そのものであるという点も、事態の深刻さを示しています。
すでに広く流通している楽曲の修正は、ミュージックビデオの公開停止といった対応とは異なり、遥かに困難な作業となるためです。
まとめ
今回の「Number_i 歌詞 炎上」問題について、その理由と所属事務所TOBEの回答、そして今後の課題をまとめました。
炎上の理由は、Number_iの楽曲「幸せいっぱい腹一杯」に含まれる《他力本願な思考はポカホンタス》という歌詞にありました。
この「ポカホンタス」という言葉が、単なるディズニーキャラクターの名前ではなく、17世紀に実在したアメリカ先住民女性の名前であり、彼女の悲劇的な実話を隠蔽する植民地主義的な「美談」の象徴として使われてきた歴史があるためです。 さらに、現代アメリカ政治においては、明確な人種差別的スラングとしても定着しています。
この歌詞は、「他力本願」というネガティブな言葉とポカホンタスを結びつけることで、この差別的なステレオタイプを意図せず強化してしまったようです。
この問題に対する所属事務所TOBEの公式回答は、代理人弁護士を通じて発表されました。
その内容は、「差別する意図をもって使用したものではございません」と故意の差別を否定しつつも、「さまざまなご意見があることも真摯に受け止めております」として、今後は「多様な文化や価値観への配慮」を意識し、「表現のあり方について慎重に検討を重ねてまいります」というものでした。
Mrs. GREEN APPLEの「コロンブス」問題、Snow Manの「岡村寧次」問題、そして今回のNumber_iの「ポカホンタス」問題と、2024年だけで有力アーティストによる歴史認識を問われる騒動が立て続けに起きた事実は、日本のエンターテイメント業界全体に構造的な課題があることを示しているのかもしれません。
SNSで多くの人が指摘した《誰が歌詞書いてGOサイン出したんだろ》という素朴な疑問こそが、問題の核心です。
アーティスト個人の知識や注意深さに依存するのではなく、制作プロセスの中に、グローバルな歴史観や文化的感受性をチェックする体制を組み込むことが、世界を目指す日本のアーティストにとって急務の課題となっているようです。
スポンサーリンク

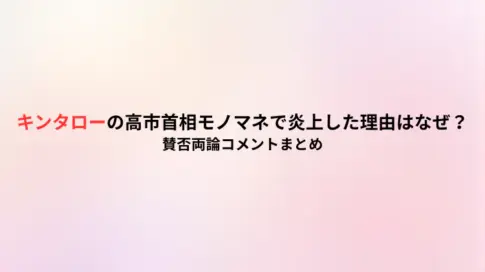









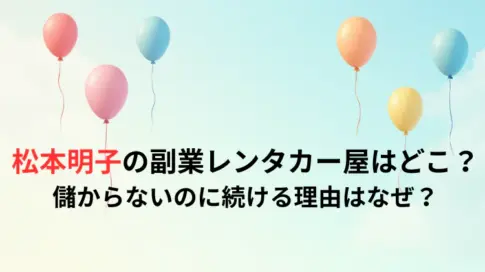

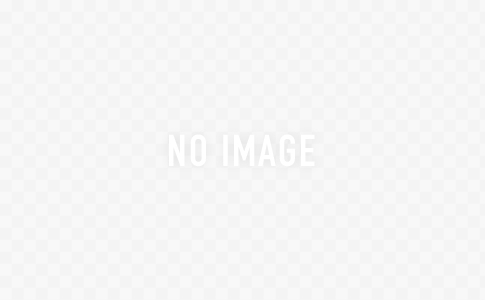



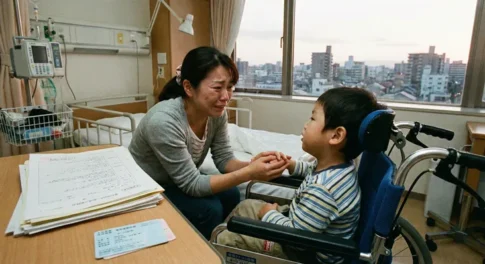







コメントを残す