スポンサーリンク
2025年9月、北海道積丹町で起きたヒグマ駆除を巡る一件のトラブルが、地域社会の安全を揺るがす大きな問題へと発展しています。報道によると、現場でのある町議会議員の発言が引き金となり、地元の猟友会がヒグマ駆除の「出動拒否」を決定するという異例の事態になりました。
積丹町のクマ駆除を巡る町議と猟友会のトラブル概要
問題の発端は、2025年9月27日に発生したヒグマの出没事案でした。
報道によれば、積丹町のある町議会議員の自宅近くに、体重284kgにもなる巨大なヒグマが現れました。この緊急事態を受け、町の要請に基づき、北海道猟友会余市支部の古平分区に所属するハンターの方が現場へ駆けつけ、駆除作業にあたりました。
現場は民家にも近く、大型の猛獣を相手にする極めて危険な状況でした。
そのため、駆除にあたっていたハンターの方は、安全確保の観点から、現場近くにいたその町議に対し、現場から離れるよう指示を出しました。これは危険な作業現場における専門家としての当然の判断だったとされています。
しかし、この安全指示が思わぬ対立を生むことになります。報道によると、町議はこの指示に激高したとされています。そして、この時のやり取りが、町と猟友会の信頼関係を根底から揺るがす深刻な事態へと発展していきました。
積丹町議の「やめさせてやる」発言理由はなぜ?
このトラブルで最も大きな焦点となっているのが、猟友会側が主張する町議の「やめさせてやる」という発言です。
猟友会側は、この発言を非常に重く受け止めました。
町の要請で危険な公務を遂行しているハンターに対し、その立場を脅かすような言葉であり、ハンター個人の尊厳だけでなく、猟友会という組織全体の名誉を著しく傷つけるものだと捉えられました。
では、積丹町議が「やめさせてやる」と発言した(とされる)理由はなぜでしょうか。この点について、両者の主張は真っ向から対立しています。
猟友会側の受け止めによれば、ハンターによる安全確保のための指示に対し、町議が感情的になり、自らの政治的な立場を利用して圧力をかけようとした、というのが理由とされています。
たとえ町議にハンターを直接解任する「権限」がなかったとしても、小さな町においては、その立場が持つ影響力は大きく、猟友会の活動にとって不利益な状況を生み出すことも不可能ではないと懸念されました。
つまり、この発言は立場を利用した「脅威」であり、権力の濫用だと受け止められたのです。
一方で、町議自身は報道機関の取材に対し、「『やめさせてやる』とは言っていない」と発言自体を明確に否定しています。さらに、「一町議がそんな力を持っているわけがない」と述べ、ハンターをやめさせるような権限は自身にはないと釈明していると報じられています。
このように、発言の理由は、猟友会側が主張する「安全指示への激高と立場を利用した圧力」と、町議側が主張する「発言の否定と権限の不在」とで、大きく見解が異なっているのが現状です。
スポンサーリンク
猟友会が「出動拒否」に至った経緯と町議の食い違う主張
両者の主張が食い違う中、猟友会の対応は迅速でした。報道によれば、トラブルが発生した翌日、積丹町の猟友会は町に対し、今後のヒグマ駆除要請には応じないとする「出動拒否」を正式に通告しました。
この決断は、単なる感情的な反発ではありません。猟友会によれば、これは組織の尊厳を守り、ボランティアであるハンターたちが不当な圧力や敬意を欠いた扱いを受けることなく、安全に活動できる環境を求めるための重大な意思表示でした。
今回の事件は、個別の口論ではなく、町との信頼関係が根本から崩れた結果と位置づけられたのです。
この「出動拒否」は、即座に地域の安全に空白を生み出しました。住民からは「実際にクマが出たら出動してもらいたい。心配だ」といった不安の声が上がっていると報じられており、地域住民の安全確保において猟友会がいかに不可欠な存在であるかが浮き彫りになりました。
出動拒否の背景にあるハンターたちの根深い不満
積丹町の猟友会による「出動拒否」は、この一件だけが理由ではない、との指摘もあります。報道によれば、北海道のハンターたちは長年にわたり、法的なリスク、危険に見合わない経済的な待遇、そして深刻な担い手不足という三重の苦しみに直面してきました。
特に、2018年に砂川市で起きた「砂川事件」は、ハンターたちに大きな衝撃を与えたとされています。この事件では、市の正式な要請でヒグマを駆除したベテランハンターの池上治男さんが、駆除時の発砲が危険だったとして猟銃の所持許可を取り消される事態となりました。
2021年には札幌地裁で勝訴したものの、2024年10月には札幌高裁で逆転敗訴となったと報じられています。要請に従って公務を遂行したにもかかわらず、法的に守られないかもしれないという現実は、「撃っても地獄、撃たなくても地獄」という状況を生み出し、ハンターたちを精神的に追い詰めているとされています。
こうした法的不安に加え、報酬の問題も深刻です。2024年には奈井江町で、ヒグマ出動の日当額を巡って町と猟友会の交渉が決裂し、猟友会が町の対策実施隊への参加を辞退する事態も起きています。
命がけの作業に対し、報酬があまりにも低いという不満が各地でくすぶっているようです。
このような積年の不満が積み重なる中で、積丹町議の発言とされる問題は、ハンターたちの最後の砦であった「最低限の敬意」すらも踏みにじるものと受け止められ、今回の「出動拒否」という断固たる決断につながったのではないか、と分析されています。
世間の反応やコメント
この積丹町での対立はメディアを通じて広く報じられ、特にソーシャルメディア上では大きな議論を巻き起こしました。
X(旧Twitter)などでは、その多くが猟友会の「出動拒否」という決断に理解と支持を示すものでした。一方で、町議の言動とされた内容に対しては厳しい批判が集中している様子が見受けられます。
ネット上では、町議の発言とされるものはその立場を利用した「権力の濫用」であり、特権意識の表れではないか、といった意見が数多く投稿されました。
また、危険な業務を担う専門家に対し、理不尽な要求や暴言をぶつける「カスタマーハラスメント」の一種だと評する声もありました。
さらに、公人としての説明責任を問う姿勢から、当該町議の氏名や所属の公開を求める声、さらには議員辞職を要求するような厳しい意見も見られました。
全体として、世論は危険な現場で地域のために活動するハンターの側に立ち、その専門性を軽んじたと見なされた言動を強く批判する傾向にありました。
まとめ
北海道積丹町で起きた、町議会議員と猟友会の対立。
その発端とされた「やめさせてやる」発言の理由については、猟友会側が「安全指示に対する激高と圧力」と主張するのに対し、町議側は「発言自体を否定」しており、両者の主張は食い違っています。
しかし、この一件をきっかけに猟友会が「出動拒否」という決断に至った背景には、単なる口論では済まされない、北海道のハンターたちが長年抱えてきた根深い問題が存在していました。
法的な立場の曖昧さ、危険な任務に見合わない報酬、そして深刻な後継者不足。これらの構造的な問題が限界に達していたところに、今回の事件が引き金となった形です。
ヒグマの出没件数が北海道全域で増加し、市民の安全がかつてないほど脅かされている中で、その最前線を担うハンターたちの活動が停止するという事態は、北海道の野生動物管理システム全体が大きな岐路に立たされていることを示しています。
スポンサーリンク

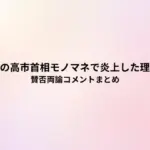
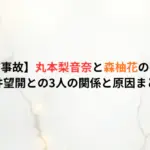

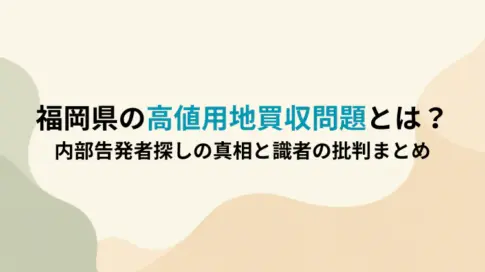
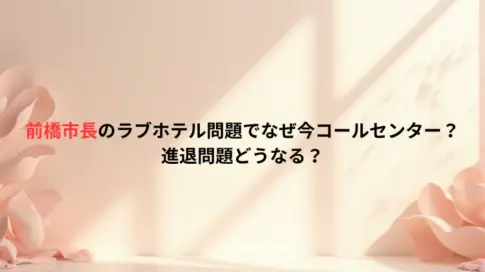
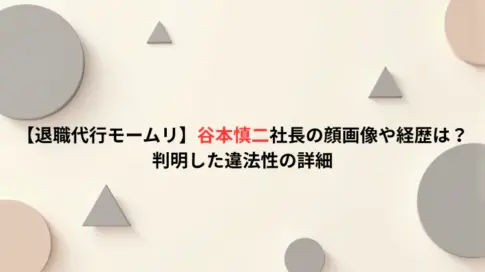
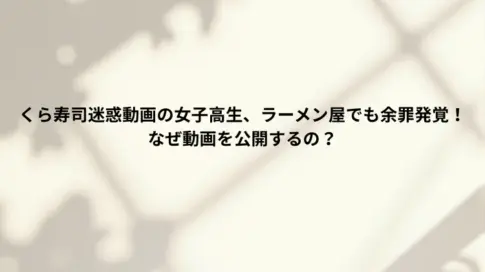














コメントを残す