スポンサーリンク
全国大会常連として輝かしい実績を誇る東邦高校サッカー部で、指導者による暴行黙認という信じがたい事件が起きました。
「暴行を黙認した顧問は一体誰なのか?」、なぜ事件は止められなかったのか、そしてどのような処分が下されたのか。
東邦高校サッカー部で何が起きた?暴行事件の概要
事件が起きたのは、5月中旬の夜のことです。
愛知県外からサッカー部に入部した1年生部員たちが共同生活を送る下宿先のアパートでした。
事件には主に3者の人物が関わっています。被害者は、親元を離れて新しい環境での活躍を夢見ていたサッカー部の1年生部員3名です。
そして、直接的な加害行為に及んだのは、部員たちが暮らすアパートの所有者である男性でした。この男性は、顧問の紹介で部員たちの食事の世話なども担当しており、生徒たちの生活に深く関わる立場でした。
最後に、この一部始終を目撃しながらも制止しなかったのが、サッカー部の顧問である男性教諭です。
事件の発端は、一部の部員が集合時間に遅れたことなどを理由に、顧問が「生活態度の指導」を始めたことでした。
しかし、その指導の途中でアパート所有者の男性が同席したことから、事態は急激に悪化します。男性は生徒たちに対し「大人をなめるなよ」などと威圧的な言葉を浴びせた後、暴力行為に及びました。
ある生徒は足を蹴られ、髪を掴まれて頭を壁に押し付けられ、他の2名の生徒も頭を叩かれるなどの暴行を受けました。
最も深刻な点は、生徒を守るべき立場である顧問の男性教諭が、目の前で繰り広げられる暴行をただ見ていただけだったという事実です。
恐怖に震える生徒たちをかばうことも、加害行為を止めることもしませんでした。後の学校側の調査に対し、被害生徒は「恐怖を感じた」と証言しており、この出来事が心に与えた傷の深さを物語っています。
本来、最も安全であるはずの場所で、生活を支える大人と部活動の指導者という二人の信頼すべき人物の前で、逃げ場のない恐怖を味わわされたのです。
暴行を黙認した顧問は誰?止めなかった驚きの理由
この事件において、最大の関心事であり、最も大きな批判が寄せられているのが、「なぜ顧問は暴行を止めなかったのか」そして「その顧問とは誰なのか」という点です。
暴行を黙認した顧問の氏名は公表されている?
まず、読者が最も知りたいであろう「暴行を黙認した顧問は誰か」という問いへの直接的な答えですが、学校や主要な報道機関から、この男性教諭の具体的な氏名は公表されていません。
そのため、個人を特定する情報は正式には明らかにされていないのが現状です。
東邦高校サッカー部の主な指導体制
顧問の個人名が非公表である一方、東邦高校サッカー部の公式サイトなどによると、チームの指導体制には中心的な役割を担う方々がいます。
ゼネラルマネージャーの道家 歩さん、監督の杉坂 友浩さん、そして総監督の石渡 靖之さんなどです。
ただし、今回事件の現場に同席し、暴行を黙認した顧問が、これらの方々のうちの誰かなのか、あるいは別の教諭なのかについて、公式な発表はなく確認されていません。
顧問が暴行を止めなかった2つの理由
学校側の調査に対して、顧問の男性教諭は暴行を止めなかった理由として、2つの説明をしています。
一つ目の理由は、「普段から部員の面倒を見てくれていた男性を信頼していたから」というものです。この説明は、教員が生徒の安全を守るという最も重要な責務よりも、アパート所有者の男性との個人的な信頼関係を優先してしまったことを示しています。
日頃からの協力関係が、目の前で行われている明らかな暴力行為を「指導の一環」であると誤認させ、生徒を守るという本来の行動を妨げた可能性があります。これは指導者としての責任を放棄したと言わざるを得ません。
二つ目の理由は、さらに衝撃的です。顧問は「寸止めに見えた」とも弁明しています。足を蹴り、髪を引っ張り、頭を壁に押し付けるという一連の行為が、どのようにすれば「寸止め」に見えるのでしょうか。
この説明は、被害生徒たちが「恐怖を感じた」と証言している現実とはあまりにもかけ離れており、常識的に受け入れがたいものです。
責任を逃れるための虚偽の説明か、あるいは暴力的な指導に対して感覚が麻痺し、行為の悪質さを認識できなかったのか、いずれにせよ指導者としての資質が根本から問われる発言です。
スポンサーリンク
顧問への処罰はどうなった?学校側の対応と今後の課題
事件発覚後、学校はどのように対応し、関係者にはどのような処分が下されたのでしょうか。そして、この事件は私たちに何を問いかけているのでしょうか。
顧問への処分は「無期限の指導停止」
保護者からの報告を受け、調査を開始した東邦高校は、今回の行為を「体罰」と認定しました。そして、生徒を守るべき責任を放棄し、暴行を黙認した顧問の男性教諭に対し、「無期限の指導停止処分」を下したと発表しました。
また、この調査の過程で、別の外部コーチによる不適切な発言も明らかになり、このコーチも指導から外されています。
「無期限」という処分は重く響きますが、将来的に指導現場へ復帰する可能性が残されているのかなど、不透明な部分も指摘されています。
被害生徒は転校へ|事件が残した最も重い結末
学校の野崎 久美子教頭は「学校として申し訳ない。顧問本人も反省している」と謝罪のコメントを発表しました。
しかし、どのような処分や謝罪があっても、失われた信頼を取り戻すことはできません。この事件がもたらした最も悲しく、重い結末は、被害を受けた生徒3名が転校を決意したことです。
報道によると、2名はすでに学校を去り、残る1名も転校の手続きを進めているとされています。夢と希望を抱いて入学した学校とサッカー部を、最も信頼すべき大人たちの裏切りによって去らざるを得なくなったのです。これは、学校にとって取り返しのつかない過ちです。
他の不祥事との比較から見える構造的問題
高校の強豪スポーツ部における指導者の問題は、残念ながら後を絶ちません。
例えば、2022年に起きた熊本県の秀岳館高校サッカー部でのコーチによる暴行事件は、監督がその事実を隠蔽しようとした点で大きな問題となりました。
今回の東邦高校の事件は、第三者による暴力を顧問が「黙認・放置」したという点で形態は異なりますが、根底にある問題は共通しています。
それは、勝利という目標や閉鎖的な人間関係の中で指導者の権威が絶対化され、生徒の人権や尊厳が軽んじられてしまうという、日本の部活動に根強く存在する構造的な課題です。
まとめ
全国的な強豪である東邦高校サッカー部で起きた今回の暴行黙認事件は、スポーツ指導の現場に潜む深刻な問題を改めて浮き彫りにしました。
「暴行を黙認した顧問は誰か」という点については未だ公表されていませんが、事件の核心は、特定の個人名以上に、生徒を守るべき指導者がその責任を完全に放棄したという事実にあります。
顧問の「男性を信頼していた」「寸止めに見えた」という弁明は、生徒たちが感じた恐怖とはあまりにも乖離しており、その判断基準の歪みを露呈しました。
学校側は顧問を「無期限の指導停止」としましたが、夢を絶たれた被害生徒3名が転校を余儀なくされたという結末は、何物にも代えがたい重い結果です。
この事件を単なる一つの学校の問題として終わらせるのではなく、すべてのスポーツ指導者が自らの襟を正し、子どもたちの安全と人権を最優先するとはどういうことかを再認識するきっかけとしなければなりません。
スポンサーリンク



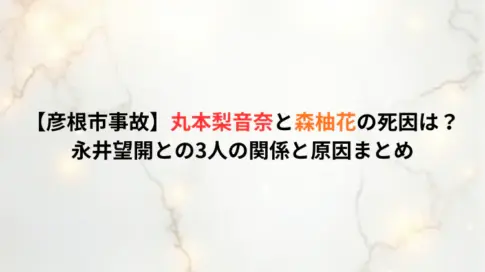

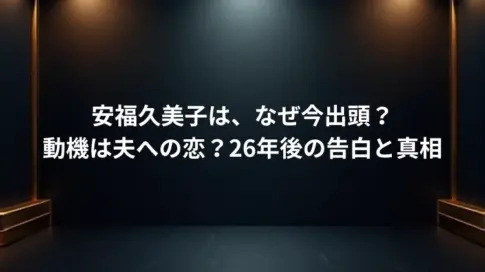

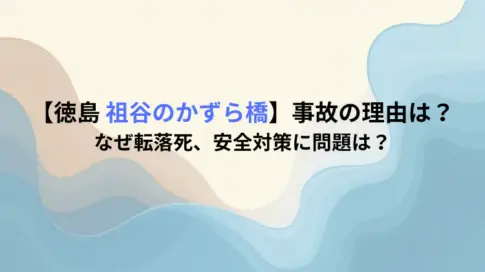
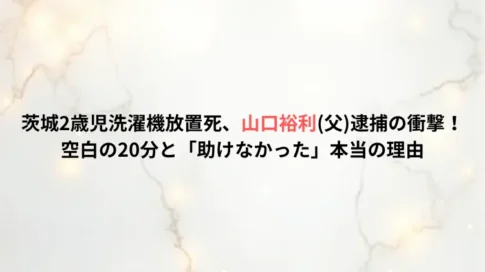





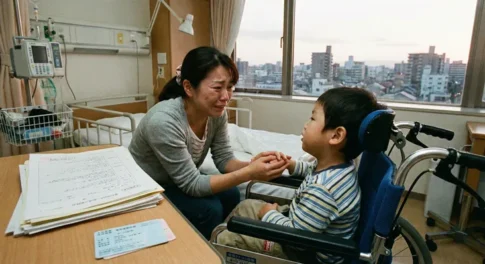







コメントを残す