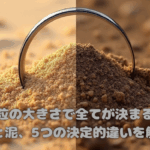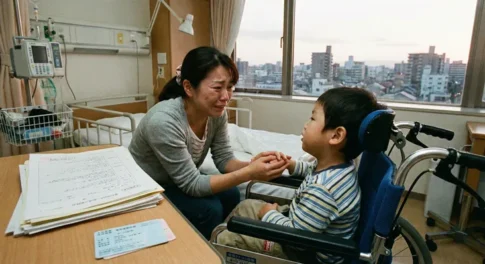スポンサーリンク
「ブッ!」という音と共に、愛犬が飛び上がってキョロキョロ。
自分のおならに驚くその姿は、なんとも微笑ましい光景ですよね。
しかし、そのコミカルな行動の裏には、犬の鋭い聴覚や嗅覚、そして「自分」をどう認識しているかという、奥深い謎が隠されています。
この記事では、専門家の知見を交えながら、犬がおならに驚く理由を徹底解説。
さらに、おならの回数や匂いでわかる健康状態のチェックポイントから、今日からできる具体的なケア方法まで、飼い主さんが知りたい情報を網羅的に解説します。
愛犬からの小さなサインを見逃さないために、一緒に学んでいきましょう。
犬が自分のおならに驚くのはなぜ?考えられる7つの理由

愛犬が自分のおならの音に「ビクッ!」と驚き、不思議そうな顔で自分のお尻を振り返る。そんな微笑ましい光景を見たことがある飼い主さんは多いのではないでしょうか。
まるで「今の音は自分じゃない!」と言っているかのような姿はとても可愛らしいですが、なぜ犬は自分のおならに驚くのでしょうか。
この不思議な行動の裏には、犬ならではの体の仕組みや感覚、そして自己認識のあり方が複雑に関わっています。ここでは、考えられる7つの主な理由を詳しく解説します。
理由1:自分のお尻から未知の「音」と「振動」がしたから
犬にとって、おならをすること自体は日常的な生理現象です。しかし、そのほとんどは音のしない、いわゆる「すかしっぺ」です。
犬は人間のようにガスを我慢する習慣がないため、こまめにガスを排出しており、体内にガスが溜まって大きな音が出ることは稀なケースなのです。
そのため、「ブッ」というような音や体で感じる振動を伴うおならは、犬にとって「いつもと違う、予期せぬ出来事」となります。
自分の体から普段はしないはずの音や振動が突然発生したことに対する、純粋な驚きと困惑が、あのキョトンとした表情に繋がっているのです。
これは、自分の体は普段こんな音を出さないという、根源的な生理学的ショックと言えるでしょう。
理由2:自分の体から発生したと理解できず困惑しているから
犬は、自分のおならの匂いを「自分のもの」だと認識する嗅覚的な自己認識能力を持っていると考えられています。
東京農業大学の増田宏司さんによると、犬が意識的におならをすることはほぼなく、「プピッ」と自分の背後あたりから音がしていることに純粋に驚いている状態であると思われます。
しかし、その音が自分の体内で起こった不随意な(意識しない)筋肉の収縮によって発生した、という一連の流れを認知的に結びつけるのは難しいようです。
聴覚的には「外部から聞こえた脅威かもしれない音」、嗅覚的には「よく知る自分の匂い」という、矛盾した情報が同時に脳に送られます。
この認知的なパズルを解こうとして、「今の音の正体は何だろう?」と自分のお尻のあたりを見つめ、混乱しているのだと考えられます。
理由3:優れた聴覚で人間には聞こえない周波数の音を捉えているから
犬の聴覚は人間よりもはるかに鋭敏です。人間の可聴周波数域が最大約20,000Hzであるのに対し、犬は最大で50,000Hzから60,000Hzの音を聞き取ることができます。
そのため、おならに含まれる高周波成分など、人間には聞こえない音を犬は捉えている可能性があります。
私たちには些細な音に聞こえても、犬にとってはより耳障りで衝撃的な音として知覚されているのかもしれません。
また、犬は音の方向を約32方向から聞き分ける正確な音源定位能力を持っています。
それゆえに、すぐ後ろから聞こえる音の発生源を視覚的に特定できない状況が、より大きな混乱を招いている可能性も指摘されています。
理由4:鋭い嗅覚でいつもと違う自分の匂いに戸惑っているから
犬は「匂いの世界の住人」と言われるほど、嗅覚が発達しています。犬の鼻には最大3億個もの嗅覚受容体があり、これは人間の約600万個を圧倒的に上回ります。
この鋭い嗅覚によって、犬は自分のおならの匂いを詳細に分析し、「自分のものだ」と認識できます。
しかし、食べたものによっては、いつもと違う匂いのおならが出ることがあります。例えば、高タンパクな食事は硫化水素など、特に強い匂いのガスを発生させる原因になります。
アレクサンドラ・ホロヴィッツさんの研究では、犬が自分自身の匂いの平常時との違いを認識できることが示唆されており、いつもと違う「自己の匂い」に対して、「あれ?何だかいつもと違うぞ?」と戸惑い、確認している可能性も考えられます。
理由5:「いけないことをした」と飼い主に怒られるかもしれないと思っているから
犬の反応は、過去の経験によって学習され、形成されることがあります。
もし、犬がおならをした時に、飼い主が大きな声で驚いたり、あるいは音の原因を誤解して叱ってしまったりした経験があると、犬は「おならの音=良くないこと」と学習してしまう可能性があります。
その結果、おならをした後に「また怒られるかもしれない」と不安を感じ、飼い主の顔色をうかがうようなそぶりを見せることがあります。
これは、おならの音そのものよりも、その後に起こるかもしれない飼い主の反応を予測して警戒している状態と言えるでしょう。
理由6:お腹の不調など、体調の異変を本能的に察知しているから
おならの回数が急に増えたり、匂いが異常にきつくなったりした場合、それは消化不良のサインかもしれません。
犬は、お腹の張りや不快感といった体内の異変を本能的に察知し、その違和感に対して不安な反応を示すことがあります。
特に、おならが普段と違うことに加えて、下痢や嘔吐、食欲不振などの症状が見られる場合は注意が必要です。
犬がおならに驚く行動が、実は何らかの病気の初期症状である可能性もゼロではありません。
その驚きは、私たち人間に「なんだかお腹の調子が変だよ」と伝えようとしている、本能的なサインなのかもしれません。
理由7:特に深い意味はなく、単なる条件反射や癖
すべての犬が自分のおならに毎回ドラマチックな反応を示すわけではありません。特に、フレンチ・ブルドッグのように日常的に音を伴うおならをしやすい犬種では、その音に慣れてしまい(慣化)、ほとんど、あるいは全く反応を示さなくなることもあります。
また、犬の基本的な性格も反応の仕方に影響します。もともと不安傾向が強い、臆病な性格の犬はささいな音にも大きく驚くでしょうし、逆に大胆で好奇心旺盛な犬は、一瞬驚いてもすぐに忘れてしまうかもしれません。
そのため、特に深い意味はなく、その犬個有の気質や、たまたまその時の状況による単なる条件反射であるケースも考えられます。
そもそも犬はおならをするの?犬のおならの基本

ここでは、犬のおならに関する基本的な知識について解説します。
犬もおならをしますか?はい、人間と同じ生理現象です
はい、犬も人間と全く同じように、おならをします。いぬのきもち獣医師相談室の岡本りささんによると、これはごく自然な生理現象です。
口から飲み込んだ空気や、腸内で食べ物が分解される過程で発生したガスが体外に排出されるもので、健康な犬でも日常的に起こります。運動しているときや興奮したとき、食後などにおならが増える傾向があるようです。
犬のおならはどんな音?「ブッ」という音から静かな「すかしっぺ」まで様々
犬のおならの音は、状況によって様々です。多くの場合は音を伴わない静かな「すかしっぺ」ですが、体内にガスが溜まっていると、人間と同じように「ブッ」や「プー」といったはっきりとした音が出ることがあります。
犬は普段からこまめにガスを排出しているため、大きな音を伴うおならは比較的まれで、だからこそ犬自身が驚いてしまうのです。
リラックスしている時におならをしやすいって本当?
データベースにはリラックスしている時におならをしやすいという直接的な記述はありませんが、逆に運動時や興奮時、ストレスを感じている時にはおならが出やすいとされています。
これは、呼吸が速くなることで空気を飲み込みやすくなったり、自律神経の乱れが胃腸の働きに影響したりするためです。
体がリラックスし、副交感神経が優位になると胃腸の働きが活発になるため、その結果としておならが出やすくなる可能性は考えられます。
犬もおならを我慢することはできるの?
哺乳類学者の今泉忠明さんの監修記事によると、犬には人間のように意識的におならを「我慢する」という習慣はないと考えられています。
そのため、ガスが溜まれば自然に排出されます。この「我慢しない」性質が、犬のおならのほとんどが音のしない静かなものである理由の一つであり、たまに出る大きな音のおならが犬にとって「予期せぬ出来事」となる原因でもあります。
スポンサーリンク
うちの愛犬、おならが多いかも?犬のおならの回数が増える原因

愛犬のおならが他の犬より多いと感じる場合、いくつかの原因が考えられます。
原因1:早食いで空気をたくさん飲み込んでいる(呑気症)
食事を勢いよくかき込むように食べる犬は、食べ物と一緒に大量の空気を飲み込んでしまいます。これを「吞気症(どんきしょう)」と呼び、おならの主な原因となります。
特に、パグやフレンチ・ブルドッグなどの短頭種は、顔の構造上、呼吸の際に空気を飲み込みやすく、おならが出やすい傾向にあります。
原因2:フードが体に合わず消化不良を起こしている
ドッグフードの成分が愛犬の体質に合っていないと、消化不良を起こして腸内でガスが発生しやすくなります。
例えば、過剰な肉などの高タンパクな食事や、特定の野菜、ダイエットフードに含まれる豊富な食物繊維、乳製品などは、腸内でのガス産生を増加させることがあります。フードを切り替えた後におならが増えた場合は、そのフードが合っていない可能性があります。
原因3:運動不足で腸の動きが鈍っている
データベースには運動不足が直接的な原因であるとの明確な記述はありませんが、運動は腸の蠕動(ぜんどう)運動を活発にする働きがあります。
そのため、散歩の時間が短い、室内で遊ぶ時間が少ないなど、日常的な運動量が不足していると、腸の動きが鈍くなり、ガスが溜まりやすくなる可能性は考えられます。
原因4:ストレスによって胃腸の機能が乱れている
犬も人間と同じように、ストレスを感じると自律神経が乱れ、胃腸の機能に影響が出ることがあります。引っ越しや家族構成の変化、長時間の留守番、騒音など、犬がストレスを感じる状況は様々です。
ストレスによって消化機能が低下したり、不安によるパンティング(浅く速い呼吸)で空気を多く飲み込んだりすることが、おならの増加につながります。
原因5:加齢(シニア犬)による消化機能の低下
犬も年齢を重ねると、人間と同様に消化機能が徐々に低下していきます。消化酵素の分泌が減ったり、腸の動きが弱くなったりすることで、食べたものがうまく消化されずに腸内で異常発酵し、ガスが発生しやすくなります。
シニア犬になってからおならが増えたり、匂いがきつくなったりした場合は、加齢による消化機能の低下が原因かもしれません。
こんなおならは要注意!動物病院へ行くべき危険なサイン

ほとんどのおならは心配いりませんが、中には病気のサインが隠れていることもあります。
次のような場合は、注意深く様子を観察し、早めに動物病院を受診しましょう。
おならが異常に臭い場合は?
食べたものによっておならの匂いは変わりますが、普段と比べて明らかに腐敗臭のような強い悪臭が続く場合は、腸内環境が悪化しているサインかもしれません。
消化不良や腸内の悪玉菌の増加などが考えられます。特に、おならの匂いの変化とともに他の症状が見られる場合は注意が必要です。
下痢や嘔吐、血便を伴うおならの場合は?
おならの回数が急に増え、同時に下痢や嘔吐、血便といった消化器症状が見られる場合は、単なる消化不良ではなく、胃腸炎や食物アレルギー、感染症などの病気の可能性があります。
脱水症状を引き起こす危険もあるため、これらの症状が続く場合はすぐに動物病院へ連れて行きましょう。
おならと同時に食欲不振や元気がない場合は?
おならが増えただけでなく、普段より食欲がなかったり、ぐったりして元気がないといった様子が見られたりする場合も、体のどこかに異常があるサインです。犬は言葉で不調を訴えられないため、こうした行動の変化が重要な手がかりとなります。
お腹が張っている・痛がるそぶりを見せる場合は?
お腹がパンパンに張っていたり、触られるのを嫌がったり、お腹を抱えるような姿勢をとったりする場合は、腸内にガスが過剰に溜まっているか、腹部に痛みを感じている可能性があります。
このような行動は、犬にとってかなりの苦痛を伴う状態であり、緊急を要する病気が隠れていることもあります。
考えられる病気一覧(胃腸炎・膵炎・腫瘍など)
おならの異常がサインとなる可能性のある病気には、炎症性腸疾患(IBD)、急性または慢性の胃腸炎、膵炎、食物不耐性、さらには消化管の腫瘍など、様々なものが考えられます。
たかがおならと軽く考えず、他の症状と合わせて総合的に判断し、少しでもおかしいと感じたら獣医師に相談することが重要です。
愛犬のおなら対策!今日からできる4つの改善ケア

愛犬のおならが気になる場合、日常生活の中で改善できることがいくつかあります。
対策1:フードの与え方を見直す(早食い防止食器の活用)
早食いが原因でおならが増えている場合は、フードの与え方を見直しましょう。一度に与える量を減らして食事の回数を増やしたり、内部に凹凸がある「早食い防止食器」を活用したりするのが効果的です。ゆっくり食べることで、空気の飲み込み(吞気症)を減らすことができます。
対策2:フードの種類を切り替える(消化しやすいフードなど)
今与えているフードが愛犬の体に合っていない可能性も考えられます。消化性の高い原材料を使っているフードや、アレルギーの原因になりにくいタンパク質源を使用したフード、腸内環境を整えるプロバイオティクスやプレバイオティクスが配合されたフードなどに切り替えてみるのも一つの方法です。切り替える際は、1週間ほどかけて少しずつ新しいフードの割合を増やしていきましょう。
対策3:適度な運動で腸の働きを活発にする
毎日の散歩や遊びの時間を確保し、適度な運動をさせることは、腸の蠕動運動を促進し、健康的な排便・排ガスを助けます。運動はストレス解消にもつながり、心身両方の健康維持に役立ちます。愛犬の年齢や体力に合わせて、無理のない範囲で体を動かす習慣をつけましょう。
対策4:ストレスのないリラックスできる環境を整える
犬が安心して過ごせる環境を整えることも、おなら対策には重要です。犬が一人で静かに休める寝床を用意したり、過度な刺激や騒音を避けたり、留守番の時間を短くする工夫をしたりするなど、愛犬のストレス要因をできるだけ取り除いてあげましょう。飼い主との穏やかなふれあいの時間は、犬にとって最高の安心材料になります。
犬と飼い主のおならにまつわるQ&A

ここでは、犬のおならに関するよくある質問にお答えします。
犬は飼い主のおならに気づく?どんな反応をする?
犬の優れた聴覚と嗅覚を考えれば、犬が飼い主のおならに気づく可能性は非常に高いでしょう。人間には聞こえないような小さな音や、わずかな匂いも敏感に察知しているはずです。
反応は犬の性格やその時の状況によって様々で、特に気にしない犬もいれば、音に驚いたり、匂いを嗅ぎに来たり、不思議そうな顔で飼い主を見つめたりすることもあるかもしれません。
犬がおならをした後に飼い主の顔を見るのはなぜ?
犬がおならをした後にじっと飼い主の顔を見つめることがあります。これは、自分のお尻から聞こえた不思議な音の発生源がわからず、飼い主に「今の音は何?」「大丈夫?」と助けを求めたり、説明を求めたりしているのかもしれません。
また、過去に叱られた経験から不安を感じて様子をうかがっている場合や、部屋にいる他の人やペットを見て「犯人はあっちだよ」と飼い主に訴えているかのように振る舞う、ユニークなケースも報告されています。
犬がおならをした時に笑うのはNG?正しい接し方とは
犬がおならをした時に飼い主が笑うと、犬は「注目された」「喜んでくれた」と学習し、その行動が強化される可能性があります。
特に問題行動というわけではありませんが、もし犬が音に驚いて怖がっているようであれば、笑うのではなく、「大丈夫だよ」と優しく声をかけて安心させてあげるのが良いでしょう。
逆に、大げさに驚いたり叱ったりすると、犬に不必要な不安や恐怖を与えてしまうため避けるべきです。何事もなかったかのように、冷静に接するのが基本です。
おならをしやすい犬種はいる?(フレンチブルドッグ、パグなど)
はい、おならをしやすい傾向のある犬種は存在します。特に、フレンチ・ブルドッグ、パグ、ボクサーといった鼻の短い「短頭種」は、その骨格構造から食事や呼吸の際に空気を飲み込みやすく、おならが多くなる傾向があります。
もし短頭種の愛犬のおならが多いと感じても、他の症状がなければ、それは犬種特有のものかもしれません。
びっくりする様子が可愛い「おならびっくり動画」はなぜ人気?
SNSなどで犬が自分のおならに驚く動画が人気を集めるのは、その反応が非常に人間味あふれ、コミカルに見えるからでしょう。
予期せぬ音に飛び上がったり、真剣な顔で自分のお尻を犯人探しのように見つめたりする姿は、純粋で無垢な犬の性格を象徴しており、見る人の心を和ませます。
その行動の裏にある科学的な理由を知ると、さらにその可愛らしさが深まるかもしれません。
まとめ:愛犬のおならは健康のバロメーター。日々の変化を見守ろう

最後に、この記事の要点を改めて振り返ります。
犬がおならに驚く理由と原因をもう一度おさらい
犬が自分のおならに驚くのは、単なるおかしな癖ではありません。
それは、音を伴うおならが犬にとって「予期せぬ出来事」であること、その音や匂いを犬の鋭敏な感覚が強烈に捉えること、そして「外部の音」と「内部の匂い」という矛盾した情報を脳が処理しきれずに混乱することなど、生理学・感覚・認知の各側面が複雑に絡み合った結果なのです。
たかがおならと侮らず、愛犬からのサインを見逃さないで
普段のおならは心配ありませんが、その回数、音、匂いは愛犬の健康状態を示す重要なバロメーターです。
食事内容やストレス、運動量など、日々の生活がおならに反映されます。愛犬のおならの変化に気づくことは、体調の変化を早期に発見するきっかけにもなります。
少しでも不安なことがあれば、かかりつけの獣医師に相談を
おならの回数や匂いが急に変わったり、下痢や嘔吐、食欲不振といった他の症状を伴ったりする場合は、何らかの病気が隠れている可能性も考えられます。
愛犬の様子で少しでも気になること、不安なことがあれば、自己判断せずに、かかりつけの動物病院で獣医師に相談してください。
参考情報
関連記事
免責事項
本記事の内容は、提供された情報源に基づき作成されたものであり、特定の犬の症状や健康状態について診断・治療を行うものではありません。愛犬の健康に関する具体的な問題については、必ず資格を有する獣医師にご相談ください。
スポンサーリンク