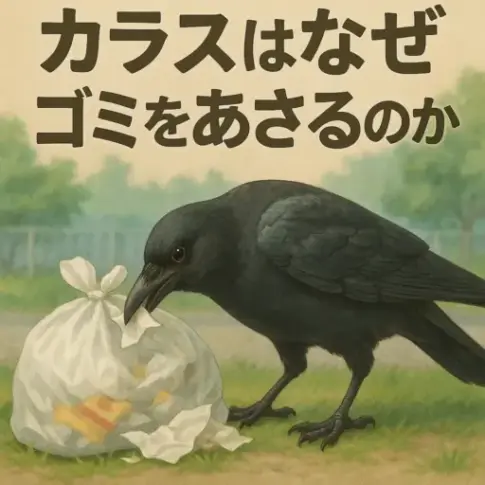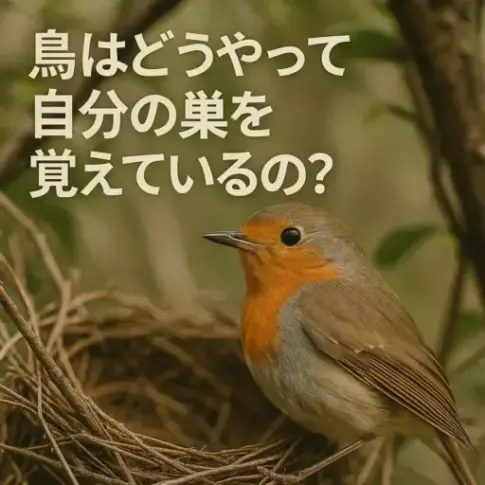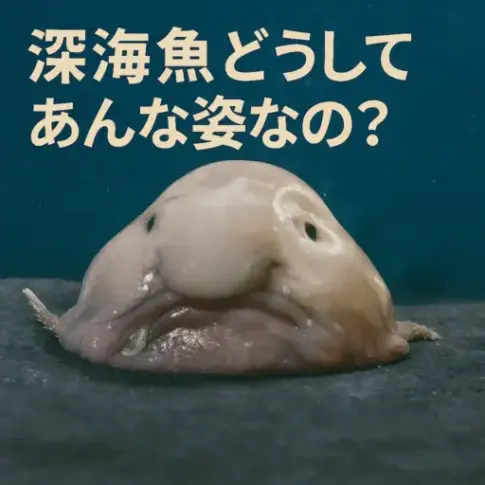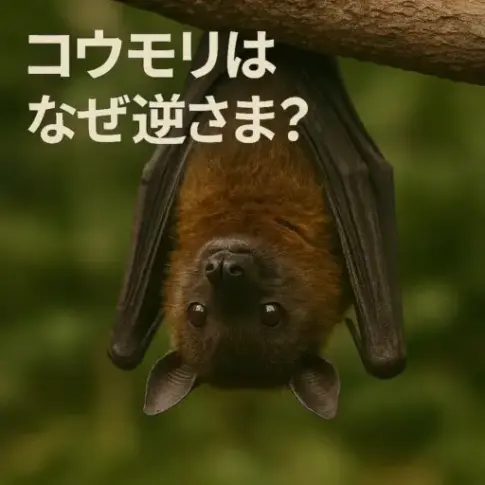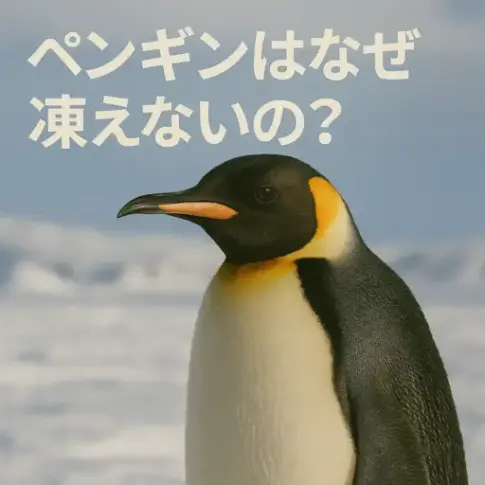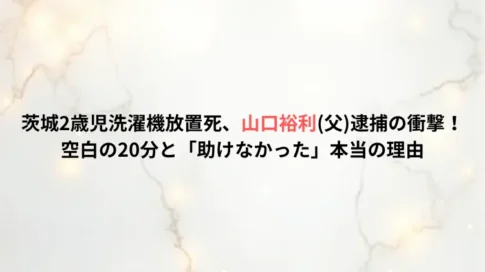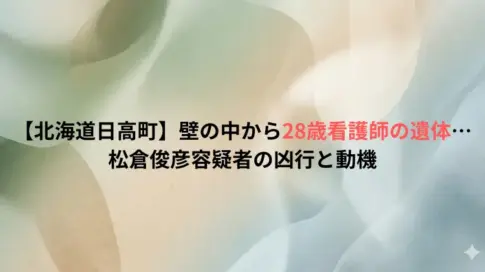スポンサーリンク
カラスが光るものを好んで集めるという話は、私たちの文化に深く根付いた俗説として広く知られています。
物語や漫画では、カラスが宝石やガラス片を盗む姿が描かれ、実際にビー玉や瓶の破片といった輝く物体にカラスが興味を示し、巣に持ち帰るという目撃談も後を絶ちません。
しかし、この広く信じられている行動の真相は、科学的な視点から見ると全く異なる姿が浮かび上がってきます。
この記事では、カラスと光るものにまつわる長年の謎を科学の光で照らし、その真実を解き明かしていきます。
カラスは光るものが好き?専門家の答えは「実は用心している」

カラスが光るものを特に好きで集める、という広く信じられている話は、実は科学的な証拠がほとんどない「うわさ」だとわかってきました。
本当のところは、カラスのとても高い頭の良さや、何でも知りたがる気持ち、私たち人間とは違うものの見方、さらには「初めて見るもの」に対する複雑な心の動きが関係しているのです。
「カラス=光るものが好き」は間違い?長年のうわさの秘密とは
「カラスが光るものが好き」って話、どうしてこんなに広まったのでしょうか?このうわさの秘密を一緒に見ていきましょう。アニメやマンガでは、カラスがキラキラしたものを集めて巣を飾るのがよくあります。
しかし、実はそれを証明する科学的な証拠はほとんどないのです。市役所からの注意や専門家の話でも、「カラスが光るものが好き」という説には、科学的な根拠がないとはっきり言われています。
もしカラスが光るものを巣に持っていくことがあったとしても、それは特別な理由や「これが好きだから」っていう気持ちでやっているわけではないのです。
このうわさが広まったのは、直接的な理由はないですが、昔からの物語や文化が関係しているのかもしれません。
例えば、北アメリカのハイダ族っていう人たちの昔話では、ワタリガラスが太陽のかけらを持ってきて、世界を明るくしたって言われています。
しかし、実際のカラスの暮らしとは分けて考えないといけないのです。
なぜ「光るものが好き」という話が広まったのか?
「カラスは光るものが好き」っていう噂は、科学的な証拠ではなく、人間が「やっぱりそうなんだ!」と思い込みやすい気持ちや、動物に人間の気持ちを当てはめてしまうことで広まったと考えられています。
人は、頭の良いカラスが珍しいもの(例えばビンのフタとか)をじっと見ているのを見ると、「カラスは光るものが好き」っていう元々持っていた考えが強くなるのです。もしそれがたまたま光っていたら、なおさらでしょう。
しかし、カラスが光らない小枝や落ち葉、紙くずとかを調べている姿は、この話に合わないから見過ごされちゃうことが多いのです。
私達は、カラスの行動に人間と同じ気持ちを当てはめて考えてしまいがちです。
最新研究で判明したカラスの本当の習性「新奇恐怖」
「光るものが好き」っていう評判は、カラスの仲間であるカササギにもあります。しかし、これは科学的な実験で「違うよ」とはっきり否定されました。
ドイツの『アニマル・コグニション』っていう科学の雑誌に載った研究では、カササギの行動がとても詳しく調べられています。
研究者たちは、エサ場の近くにキラキラ光るもの(金属のネジやアルミホイル)と、光らないけど形や色が同じものを置いてその後の様子を観察します。
その結果は、うわさとは全く逆でした。カササギは光るものにすごく警戒して、近づくまでに時間がかかったり、触る回数もすごく少なかったのです。
この発見は、カラスの仲間でも「光るものが好き」という噂が、科学的には間違っていることをはっきり示した結果として重要な証拠となります。
むしろ、この行動は「ネオフォビア」つまり「初めて見るものが怖い」っていう、全く逆の習性があることを示しています。このネオフォビアは、野生の動物にとって、知らないものは危ないものかもしれないし、食べたことのないものは毒かもしれない、っていう、生きるためにとても大事な本能なのです。
特にカラスの仲間は、鳥の中でも「初めて見るものが怖い」っていう気持ちが強いグループとして知られています。
では、カラスが光るものを集める本当の理由は何?

カラスが物を運ぶのは、集めているわけではないとしたら、本当は何のために運んでいるのでしょうか?実は、彼らが生きる上で役立つ行動を、僕たちが勘違いしていることが多いのです。
理由1:正体不明のものを警戒し、安全か確認するため
カラスは、「初めて見るものが怖い」という気持ち(ネオフォビア)と、「新しいものに興味がある」という気持ち(ネオフィリア)の間で、いつも揺れ動いています。
光るものを見つけた時、まずカラスは「これ、何だろう?見たことないし、変な光り方をしている。もしかしたら危ないかも」と警戒します。これは、カササギの研究でも見られた、最初にためらったり用心したりする様子と同じです。
しかし、同時に「エサになるかもしれないし、面白い遊び道具になるかもしれないな。僕は賢いから、これが何なのか確かめられるはずだ」という好奇心もわいてきます。
この二つの気持ちの間で悩んだ結果、カラスは最終的な行動を決めます。例えば、無視したり、軽くつついてみたり、安全な場所に運んでもっと詳しく調べたりするのです。
この行動は、カラスの性格や、これまでの経験、その時の状況によって大きく変わります。物を持ち去る行動は、集めているわけではありません。
もしかしたら役立つかもしれない、あるいは危険かもしれない物を、もっとよく調べるために安全な場所に動かす、という作戦なのです。
理由2:巣の近くにある危険な異物を排除するため
開けた場所で、知らないものをじっくり調べるのは危険なこともあります。他のカラスに取られてしまったり、敵の動物や車が来るかもしれないからです。頭の良いカラスなら、この危険はよくわかっています。
だから、まずその物を安全な場所に持っていって、後でゆっくり調べようと考えるのです。例えば、物を拾って、安全な木の枝や屋上へ飛んでいくことがあります。人間が見ると「巣に持って帰って集めているのかな?」と思うかもしれません。
ですが、カラスからすると、これは「とりあえず物を手に入れて、それからじっくり考える」という作戦なのです。もしその物が、エサでもないし、便利な道具や遊び道具でもないとわかれば、すぐに捨ててしまうこともあります。
だから、カラスの巣が、実はキラキラしたガラクタでいっぱいではない、という理由がこれでよくわかるでしょう。
理由3:若いカラスが好奇心や遊びで触っている
カラスの研究をしている樋口広芳さんは、カラスの行動で特に面白いのが「遊び」に似た行動だと話しています。公園の滑り台を滑り降りたり、雪の積もった屋根を背中で滑ったり、電線に逆さまにぶら下がったり、物を空から落として地面に落ちる前にキャッチしたりと、生きるために直接関係なさそうな行動がたくさん見られているのです。
これらの行動は、親や仲間から無理やりさせられているわけではありません。特別な目的があるようにも見えません。まさに、自分から楽しむためにやっていると考えられます。
このような「遊び」は、動物の世界では珍しいことです。人間や一部のサルなどの哺乳類でしか、はっきりとは見られません。
この「遊び」という見方で考えてみると、「光るものを集める」と見られていた行動も、全く違う意味になります。カラスがガラスの破片を拾い上げるのは、ただ集めるためではありません。純粋に「これ、どんなものかな?」という好奇心から、その物の重さや触り心地、光の反射の仕方などを確かめている「物を使った遊び」の一つである可能性が高いのです。
カラスは特に街の中でとてもうまく生きている動物です。人間の出す生ゴミなど、たくさんのエサを手に入れられるので、他の多くの動物のように一日中エサを探す必要がありません。
この「時間があること」が、彼らの高い頭の良さを刺激し、尽きることのない好奇心の元になっているのです。
彼らは、自分の周りの環境を調べて、新しいことを学んだり、どこまでできるか試したりする時間や考える力を持っています。この探求する行動が、人間から見ると、目的もなく物を集めているように見えることがあるのです。
食べ物と勘違いしている可能性はある?
カラスは、「貯食」という行動をよくします。これは、エサがたくさんある時に、余った食べ物を木の穴や葉っぱの下などに隠しておきます。
そして、エサが少ない時に掘り出して食べるという、とてもかしこい生きるための作戦なのです。ハシブトガラスは木の穴を、ハシボソガラスは草むらや石の下などをよく使います。
この貯食の行動には、「物を拾い上げて、別の場所に運んで隠す」という一連の動きが含まれています。
もしカラスが、食べ物と間違えて、あるいは「食べられるかな?」と試すために、食べ物ではない物(例えば、神社に置いてある石鹸やロウソクなど、実際にカラスが食べるのを見たという報告もあります)を運んだとしたら、その行動は簡単に「何かを集めている」と勘違いされてしまうことがあるのです。
スポンサーリンク
カラスがキラキラしたものを集めた後の使い道は?

カラスが物を運ぶ行動は、人間から見ると「何かを集めている」ように見えるかもしれません。しかし、本当の目的は、役に立つことや、ただ「これって何だろう?」という好奇心から来ていることが多いのです。
カラスは巣に光るものを飾るって本当?
カラスの巣は、飾り付けをするためのものではありません。巣は、ヒナを育てたり、安全に過ごしたりするための、実用的な作りになっています。
カラスが物を触ったり運んだりするのは、遊んでいるか、役に立つかどうかを確かめているかのどちらかだと思われます。
綺麗なものとして楽しんでいるわけではありません。もしカラスがエサではない物を運んでいるのを見たら、それはたぶん、生きるための行動の続きだと考えるのが一番自然です。
例えば、「これは食べ物かな?とりあえず隠しておこう」と間違えていたり、「これは道具や遊び道具として使えるかもしれない」と考えて手に入れたり、あるいは危険から身を守るための作戦だったりするのです。美しいからではなく、役に立つか、面白いか、という気持ちが動機になっているのです。
「カラスの恩返し」でプレゼントをくれることはある?
カラスのオスは、繁殖の時期になると、メスに求愛行動をします。その時に、「プレゼント」を渡すことがあるのです。
このプレゼントは、たいていエサ(求愛給餌)や、巣を作るための小枝など、実用的なものです。
時には、霜柱や水など、物としての価値よりも、プレゼントをあげるという行動自体が大切だと考えられる例も観察されています。光る物がこの求愛のプレゼントとして使われる可能性は、完全に否定することはできません。
しかし、それがカラスの一般的な習慣だというはっきりした証拠はありません。この行動は、繁殖の時期という特別な時に限られたもので、一年中見られるような「物を集める」習慣とは全く違うものなのです。
カラスがお金やアクセサリーを集めるといううわさの真相
カラスが宝石を盗む、というロマンチックなうわさは、確かに魅力的かもしれません。
しかし、その裏には、人間とは違う感覚や、生きるための大変さによって生まれた、特別な賢さがあります。
カラスは、私たち人間にはない感覚を使って、初めて見る物に触れて、学んだり、遊んだり、危険かどうかを判断したりする、とても高度な頭の働きをしています。
お金やアクセサリーを特別に集めるという科学的な根拠はないのです。
なぜカラス対策にCDやキラキラテープが使われるの?効果の仕組み

不思議なことに、「カラスは光るものが好き」といううわさと同時に、「光るものはカラスを追い払うのに効く」という話もよく聞きます。
実際に、使わなくなったCDや光を反射するテープなどが、カラス対策としておすすめされることがあります。
光るものを「嫌う」のではなく「警戒する」習性を利用していた
「カラスは光るものが好き」という話と、全く逆の「光るものはカラス除けに効く」という話は、カラスの「新奇恐怖(ネオフォビア)」という習性を利用したものです。
専門家によると、カラスが特定の光や色をいつも嫌うという事実は確認されていません。カラスを遠ざけるグッズが一時的に効くのは、それが光っているからではありません。
不規則に動いたり、光が点滅したりする様子が、カラスにとって「見たことのない、変な物」として認識されるためなのです。つまり、カラスが元々持っている警戒心を刺激しているのです。
カラスがCDやテープの乱反射を怖がる科学的な理由
カラスがCDやテープの乱反射を怖がるのは、その光が予測できない動きをして、特に変に見えたり、時には危険だと感じられたりするからです。
じっとしている物にはすぐに慣れてしまうので、対策には工夫を続けることが大切だと言われています。問題の本質は、光っているのが好きかどうかではありません。初めて見る物への反応なのです。
光る物の多くは人間が作ったもので、自然の中では珍しい存在です。カササギの研究や、カラスを遠ざけるグッズの例は、カラスの仲間が、知らない光る物に対して最初に感じる気持ちは、魅力的だというよりは、警戒心だということを示しています。
本当に効果的なカラス対策グッズと使い方
カラス対策グッズが一時的に効果を発揮するのは、その物体が「光っているから」ではありません。不規則な動きや光の点滅が、カラスにとって「見慣れない未知の物体」として認識されるためです。
静止した物体にはすぐに慣れてしまうため、対策には継続的な工夫が必要だとされています。したがって、カラスを慣れさせないために、定期的に設置場所を変えたり、複数の種類の対策グッズを組み合わせたりすることが効果的です。
注意点:カラスを慣れさせないための設置のコツ
街に住むカラスは、田舎に住む仲間よりも大胆です。知らないものを調べてみようとする気持ちが強いのです。街での生活そのものが、カラスに元々持っている怖がる気持ちを抑えさせて、もっと大胆に行動するように促している、あるいは、そういうカラスだけが生き残っていると考えられます。
そのため、カラス対策グッズは、カラスがその物に慣れてしまわないように、いつも変化を与えることが大切です。同じ場所に同じ物を置き続けると、カラスはそれが危なくないものだと学習してしまい、効果が薄れてしまうのです。
カラス以外にも光るものが好きな動物はいる?

鳥の中で本当に「物を集める」行動をする動物がどんなものかを知るには、オーストラリアやニューギニアにいるニワシドリという鳥を見ると、とてもよくわかります。
ニワシドリ:青く光るもので巣を飾りメスに求愛する鳥
ニワシドリのオスは、自分の巣とは別に「あずまや」と呼ばれる、とても凝った建物を作ります。これは、メスを誘い込むためだけの、求愛の舞台なのです。
そして彼らは、そのあずまやを飾るために、特定の色をした物を一生懸命集めて並べます。青い鳥の羽、色鮮やかな木の実、虫の羽、最近では青いペットボトルのキャップやプラスチックの破片まで、そのコレクションは本当に様々です。
このコレクションの質や美しさが、彼が子孫を残せるかどうかを直接決めるのです。これは、はっきりとした目的を持った、美しいものを集める行動の代表例です。
カラスには、このような行動は全く見られません。カラスの巣は、機能が一番大切にされた作りで、飾り付けはしません。
カラスが物に触れたり運んだりするのは、遊んでいるか、役に立つかを確かめているかのどちらかです。美しいからではありません。ニワシドリという、究極のコレクターと比べることで、カラスには本当に「物を集める」行動がないことが、よりはっきりするでしょう。
【Q&A】カラスに関するその他のよくある質問
Q. カラスの知能はどれくらい賢いの?
カラスの知能は、鳥の中でも特に優れていて、一部のサルにも匹敵すると言われています。彼らの脳には、神経細胞(ニューロン)がぎっしり詰まっていて、複雑な問題を解決する能力を支えています。
その賢さを示す一番有名な例は、道具を使うことや、自分で道具を作ることです。
南の海にいるカレドニアガラスは、小枝を加工してカギのような道具を作り、朽ちた木の中に隠れている虫を効率よく釣り出すことが知られています。これは、ただの本能ではありません。学習されて、仲間同士で伝えられる「文化」的な行動なのです。
さらに、彼らは高度な問題解決能力や、原因と結果を理解する力も持っています。日本のカラスが、硬いクルミを道路に置いて、車にひかせて割る行動はその代表的な例です。彼らはただ道路に置くだけではありません。
車が通りそうな場所を狙ったり、赤信号で止まった車のタイヤの前に正確に置いたりと、作戦を調整します。これは、行動の結果を予測する先を読む力に基づいています。
彼らの賢さは、仲間との関係の中でも発揮されます。カラスは人間の顔を一人ひとり見分けて、敵と味方を覚え、その情報を仲間と共有することさえできます。
また、見つけたエサの量や種類によって鳴き声を変えるなど、複雑な声でのコミュニケーションも行います。
Q. カラスの視力は良い?人間とどう違うの?
カラスの目の能力は、僕たちが「光る」という言葉でまとめてしまう現象を、全く違う見方で捉えています。私たち人間は、赤・緑・青の3種類の光を感じる細胞(錐体細胞)で色を見ています。これを「三色型色覚」と言います。
しかし、カラスは人間には見えない「近紫外線(UV)」を感じるための4番目の細胞を持っています。これを「四色型色覚」と言います。
さらに、彼らの目の奥には「油球」と呼ばれる特別なフィルターがあって、これが色の見分け方をさらに正確にしています。これは、カラスが私たちとは全く違う感覚の世界で生きていることを意味します。
彼らは、僕たちには文字通り見えない色や模様を知ることができます。例えば、果物の熟れ具合や、水面の光の反射、仲間の羽の状態などを、紫外線情報も合わせて判断している可能性があるのです。
僕たちにとっては何でもない風景が、カラスの目には鮮やかな色や情報でいっぱいの世界に見えているのです。
この優れた目の能力を探るため、ある実験で、本物のハムと食品サンプルをカラスに選ばせたところ、紫外線がある環境でだけ、両方を正確に見分けることができました。
これは、カラスが物の見分けに紫外線情報を積極的に使っていることを示しています。有名な「黄色いゴミ袋」の話も、この文脈で理解できます。このゴミ袋がカラス除けに効くのは、カラスが黄色を嫌いだからではありません。
その理由は、袋の素材に紫外線を吸収する物質が使われているためなのです。カラスは紫外線を頼りに袋の中身を透かして見ているので、紫外線をカットされると、中の生ゴミが見えにくくなるのです。
これは、彼らの目の世界が僕たちのそれとどれほど違い、生きるための作戦にどれほど直接つながっているかを示す良い例ですし、とても面白い話ですね。
まとめ 「カラスは光るものが好きというわけではない」

カラス対策にCDやキラキラテープが使われるのは、カラスが光るものを「好き」なのではなく、「初めて見るものが怖い」という習性を利用しているからです。専門家によると、カラスは特定の光や色をいつも嫌うわけではありません。これらのグッズが一時的に効くのは、不規則な動きや光の点滅が、カラスにとって「見たことのない、変な物」に見え、警戒心を刺激するためです。
カラスは予測できない光の動きを怖がりますが、じっとしている物にはすぐに慣れてしまいます。そのため、対策には定期的に設置場所を変えたり、複数のグッズを組み合わせたりして、カラスが慣れないように工夫することが大切です。
カラス以外で本当に光るものを集める鳥にはニワシドリがいます。彼らはメスに求愛するために、青く光る物などで美しい「あずまや」を飾ります。これはカラスの行動とは異なり、美しさを目的とした収集行動です。カラスの仲間であるカササギも、光る物に対してはカラスと同じように警戒心を示すことが、科学的な研究でわかっています。
参考情報
関連記事
- カラスはなぜゴミをあさるのか その驚きの知能と理由 そして賢いカラスとの共存のヒント
- なぜ?鳥が電線に止まっても感電しない理由をスッキリ解説!
- 鳥の巣の記憶と渡り鳥のナビゲーション 不思議な能力の謎に迫る
免責事項
本記事は、提供されたデータベースの情報のみに基づき作成されています。記載された情報は、特定の時点での科学的知見や専門家の見解を反映したものですが、常に最新の研究結果や状況の変化によって更新される可能性があります。本記事の内容は、いかなる行動を推奨または保証するものではなく、読者の皆様ご自身の判断と責任においてご活用ください。本記事の情報の利用によって生じたいかなる損害についても、筆者および提供元は一切の責任を負いません。
スポンサーリンク