スポンサーリンク
9月6日に放送されたフジテレビ「有吉の夏休み2025 密着77時間in Hawaii」で有吉弘行さんが野呂佳代さんに対し体型に対してのイジリを連発した内容による波紋によりSNSでは炎上問題となっています。
有吉弘行から野呂佳代へのイジリが炎上!番組での具体的な発言とは?
今回の炎上を理解する上で重要なのは、単発の冗談ではなく、番組を通して特定のイジリが執拗に繰り返された点です。視聴者が問題視した、有吉弘行さんから野呂佳代さんへの具体的な言動を紹介します。
繰り返された「体型イジリ」というパターン
炎上の直接的な原因は、有吉弘行さんによる野呂佳代さんの体型に関する執拗なイジリでした。番組内で有吉弘行さんは、野呂佳代さんを「大食いキャラ」として扱い、繰り返し体型に言及する発言を続けたのです。
特に象徴的だったのが食事の場面です。有吉弘行さんは野呂佳代さんに対し、「全然太ってないよ」「やせる必要ないじゃない?素敵なんだから」と、一見褒めているような言葉をかけました。
しかし、その際に笑いをこらえきれない様子だったため、多くの視聴者は言葉の裏にある意図を読み取り、強い不快感を抱きました。
また、ゴルフの話題で野呂佳代さんが小学生時代にゴルフを習っていたと明かすと、有吉弘行さんは「たしかに、天才ゴルフ少女っぽいもんな」と発言。この発言も、視聴者は野呂佳代さんの体型を念頭に置いたイジリと受け取りました。
これらの言動が一度きりなら見過ごされたかもしれませんが、番組を通して何度も繰り返されたことで、視聴者は単なる冗談ではなく悪意ある揶揄だと捉えたと考えられます。
批判の矛先は、有吉弘行さんだけに向かったわけではありません。共演者の池田美優さんがイジリを止めず、同調して笑っていたことに対しても、視聴者から厳しい声が上がりました。
SNSでは「有吉に慣れすぎてて、野呂さんへの礼を欠いていた」といった指摘が見られます。野呂佳代さんがプロとして笑顔で対応し、笑いに変えようと努めていた姿と対比する形で、池田さんの態度が問題視されたのです。
この現象は、視聴者がテレビ番組に求める倫理観の変化を浮き彫りにしています。イジリを行う当事者だけでなく、それを黙認したり、笑って同調したりする「傍観者」の存在もまた、問題の一部であると認識されるようになっていると考えられます。
有吉の毒舌芸はなぜ不快?「時代遅れ」と視聴者が感じる3つの理由
有吉弘行さんの「毒舌芸」は、かつて多くの支持を集めましたが、なぜ今、「時代遅れ」と批判されるのでしょうか。
その背景には、視聴者の価値観の大きな変化があります。有吉弘行さんの毒舌芸が「時代遅れ」だと視聴者に感じられる理由は、主に3つの社会変化に求められます。
理由1:ルッキズムへの抵抗とボディポジティブの浸透
今回の炎上で最も多く見られたのは、人の容姿を笑いの対象にすること自体への拒否反応です。現代の視聴者は、テレビで発信されるメッセージが社会に与える影響に非常に敏感です。
特に、人の外見を揶揄する笑いは、現実世界でのイジメや自己肯定感の低下に繋がりかねない、社会的に有害なものと見なすようになっています。
有吉弘行さんのイジリが批判されたのは、単に面白くなかったからではなく、「人の外見で価値を判断すべきではない」という現代の倫理観と対立したためです。
理由2:可視化された「権力勾配」
有吉弘行さんは番組のホストであり、芸能界で絶大な影響力を持つ存在。一方、野呂佳代さんは同じ事務所の後輩タレントです。
視聴者がこの明確な「先輩-後輩」という権力勾配を読み取ったことも、イジリが不快感を与えた大きな理由と考えられます。 このような関係性で後輩の野呂佳代さんが笑顔で対応する姿は、自発的な「芸」ではなく、立場の弱い者が取らざるを得ない「処世術」として視聴者に映りました。
多くの視聴者は、まるで職場のパワーハラスメントをエンターテインメントの皮を被せて見せられているような感覚に陥ったのです。
理由3:デジタル時代における「文脈」の崩壊
有吉弘行さんのイジリ芸は、共演者との長年の関係性という「文脈」に依存しています。しかし、SNS時代では、その文脈は簡単に失われます。
番組は放送されたままだけでなく、一部が切り取られた短い動画やスクリーンショットとして、X(旧Twitter)などのプラットフォームで拡散されるからです。
この「断片化された消費」スタイルでは、77時間の特番という長い放送の中では些細に見えるやり取りも、数秒のクリップに凝縮されることで「執拗」「悪質」といった印象を強く与えてしまいます。
従来のテレビの文法で作られた笑いが、この新しいメディア環境に対応しきれなかった典型的な事例と言えるでしょう。
スポンサーリンク
専門家が指摘する「イジリ」と「イジメ」の境界線とテレビの今後
この問題は、一個人の芸風が時代に合わなくなったという話に留まりません。テレビ業界全体が直面している構造的な課題を映し出しています。
プロが見る境界線:二つの対立する哲学
専門家の間でも「イジリ」と「イジメ」の境界線には、主に二つの考え方があります。
一つは、盲目のピン芸人・濱田祐太郎さんが提示した「互いに金銭的な利益があること」という現実的な定義。この視点では、イジられる側が一方的に消費されるだけで利益を得られない場合、イジメやハラスメントに近くなります。
もう一つは、吉本新喜劇の重鎮・池乃めだかさんが語る、テレビを日常社会のルールが適用されない「聖域」と見なす伝統的な芸人観です。
この世界では、身体的特徴でさえも笑いを生む「武器」であり、外部の倫理観で裁くべきではないと主張します。今回の社会的な反発の大きさは、多くの人々が有吉さんと野呂さんの関係を「不均衡」だと感じ、前者の定義を満たしていないと判断したことを示唆します。
業界のジレンマ:コンプライアンス強化の功罪
現代のテレビ業界は、コンプライアンスを遵守する流れの中、人権侵害や差別に繋がりかねない表現を減らし、視聴者が安心して楽しめる環境を作ってきました。
しかしその一方で、専門家は「過剰なコンプライアンスは表現の幅を狭め、テレビの魅力を損なう」という懸念も指摘しています。
今回の炎上は、この流れをさらに加速させる可能性があります。有吉弘行さんのような毒舌や過激なイジリは、地上波テレビではますます存続が難しくなるでしょう。
そして、エッジの効いたコンテンツは、有料の動画配信サービスなど、より閉じたプラットフォームへ移行していく流れが加速するかもしれません。
まとめ:有吉弘行のイジリ炎上問題から考える新時代の笑い
有吉弘行さんと野呂佳代さんのイジリ炎上問題は、私たちに「これからの時代の笑いとは何か」という根源的な問いを投げかけます。
旧来の価値観が通用しなくなった今、お笑いの世界では「誰も傷つけない笑い」や「優しい笑い」と呼ばれる新しい潮流が主流になりつつあります。
例えば、2019年のM-1グランプリで注目された「ぺこぱ」や「ミルクボーイ」は、誰かを傷つけたり容姿を揶揄したりしなくても、多くの人を笑顔にできることを証明しました。
現在の視聴者は、このような笑いを積極的に求めているのです。今回の炎上は、「笑いのためなら何でもあり」という時代の終わりを告げる象徴的な出来事でした。
有吉さんのような優れた芸人に求められるのは、才能を捨てることではありません。武器の矛先を個人の身体的特徴ではなく、社会の矛盾や人間誰しもが持つおかしさへと再調整していくことではないでしょうか。
これからのテレビの笑いは、誰か一人を犠牲にせず、私たちの世界の面白さを見つけ出せる作り手の手に委ねられています。
スポンサーリンク






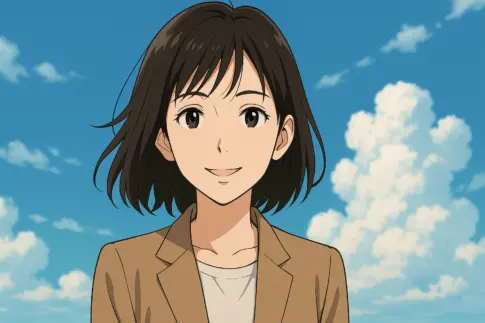















コメントを残す