スポンサーリンク
2020年代中盤を迎え、東京の青山や表参道、あるいは大学のキャンパス周辺などで、ある新しいファッションスタイルが定着しつつあります。
それは、身体のラインを隠さず、むしろありのままに見せる「全身レギンス」という装いです。
トップスにはショート丈のTシャツやパーカーを選び、ボトムスには皮膚のようにぴったりと密着したレギンスのみを着用するこのスタイル。
これに対し、年配の世代や保守的な感覚を持つ層からは、「目のやり場に困る」「身体を見せびらかしたいだけではないか」といった戸惑いの声が聞かれることもあります。
しかし、このトレンドの裏側を深く掘り下げていくと、単なる「露出願望」とは一線を画した、現代社会特有の合理的な理由が浮かび上がってきます。
本記事では、なぜ全身レギンス姿が誤解を生むのか、そして着用者たちが重視する快適性や効率性、さらには世界規模で拡大を続ける「アスレジャー」市場について解説します。
全身レギンス姿は「見せたがり」なのか?
「全身レギンス姿は、他人の関心を引くためのアピールである」という批判は、このファッションに対するもっとも典型的な誤解の一つと言えるでしょう。従来のマナーや服装規定を重視する視点から見れば、ヒップや脚のラインが露わになる服装は、周囲を誘惑しているかのような印象を与えてしまう側面があるかもしれません。
ところが、実際にこのスタイルを実践している女子大生や若手社会人の生活様式を分析すると、そこには性的な意図よりも、「時間効率(タイムパフォーマンス)」を何よりも優先する現代的な価値観が存在していることがわかります。
彼女たちの多くは、学業や仕事の合間を縫ってジムに通い、自己管理に励む過密なスケジュールをこなしています。そのようなライフスタイルにおいて、移動のたびに更衣室で着替える時間は、省略可能なコストとみなされる傾向にあります。
つまり、レギンススタイルは、ジムでのトレーニング、カフェでの友人との談笑、そして帰宅時の買い物という一連の活動を、着替えることなくシームレス(継ぎ目なし)に繋ぐための「機能的なユニフォーム」として選ばれているのです。
加えて、レギンス特有の機能性も大きな要因です。かつての補正下着や窮屈なスキニージーンズとは異なり、近年の技術で開発されたレギンスは、「第二の皮膚」と形容されるほどの快適さを備えています。
吸湿発散性に優れ、上下左右あらゆる方向へ伸縮する素材や、「ルルレモン」などのブランドが提供するバターのように滑らかな肌触りは、一度慣れてしまうと、硬い素材のボトムスには戻り難いほどの心地よさをもたらします。
彼女たちにとって、動きにくい服をあえて選ぶことは非合理的であり、自身の身体感覚を大切にするセルフケアの一環としてレギンスが採用されているのです。
さらに、昨今の「筋トレ(特にヒップトレーニング)」ブームも無視できません。K-POPアイドルなどの影響により、ただ細いだけではなく、筋肉がついたメリハリのある身体が理想とされるようになりました。
身体のラインが出るウェアは、筋肉の動きや成長を客観的に確認するためのツールとして機能します。これは他人に見せるためというよりも、鏡の中の自分と向き合い、「昨日の自分より成長しているか」を確認するという、極めてストイックな作業のために必要な要素と言えるでしょう。
「視線を気にしすぎ」批判に対する強烈な反論と欧米のファッション文化
日本の若い世代が全身レギンス姿を取り入れる背景には、SNSを通じてリアルタイムで共有される「海外のライフスタイル」への強い憧れがあります。
InstagramやTikTokなどで目にする欧米のインフルエンサーたちにとって、レギンス一枚で街を闊歩することは日常的な光景です。周囲と同じような服装を好む傾向が強い日本社会において、この「グローバルスタンダード(世界標準)」を取り入れることは、個性を表現する重要な手段となっている側面があります。
こうした状況下で、「そのような格好をしていれば、見られるのは当然だ」という批判に対し、着用者側からは「見ている側の意識こそが問われるべきではないか」という鋭い反論がなされています。
北米を中心とした欧米諸国では、レギンスはすでに日常着(ワンマイルウェア)として定着しており、それを性的な眼差しで見ること自体が時代遅れであるとされる風潮があります。彼女たちは「自分が快適で美しいと感じるから着ているのであって、他人の欲望を満たすために着ているわけではない」という、「Body Autonomy(自分の身体のことは自分で決める権利)」を主張しています。
つまり、レギンス姿を即座に性的な対象として結びつける視線こそが、見る側の自意識過剰であるという指摘です。
一方で、日本社会における現実は、それほど単純な図式では割り切れない部分もあります。日本に在住する外国人たちの間でも、日本国内でのレギンス一枚履きがTPO(時・場所・場合)に適しているかどうかは議論の的となっています。
インターネット上の掲示板などでは、日本の公共空間において身体のラインを強調することは「慎み深さに欠ける」と受け取られる可能性があるため、ヒップが隠れる長めのシャツを合わせるのが無難だというアドバイスも散見されます。
こうした外部からの視点は、日本においてレギンススタイルが文化的な摩擦を生んでいる過渡期にあることを示唆しています。それでも彼女たちが着用を続けるのは、その摩擦を乗り越えてでも得たい解放感や、グローバルな価値観を体現しているという自負があるからかもしれません。
スポンサーリンク
世界で流行する「アスレジャー」とは?
「アスレジャー」とは、「Athletic(競技)」と「Leisure(余暇)」を組み合わせた造語で、スポーツウェアを日常のファッションとして取り入れるスタイルの総称です。
この市場は世界的に急速な拡大を見せており、あるデータによれば、日本の市場規模だけでも2024年時点で約238億米ドルに達し、今後も成長が続くと予測されています。
健康意識の高まりや、リモートワークなど働き方の変化により、自宅でも外出先でも快適に過ごせるウェアが、新しい生活様式における「制服」として定着しつつあるのです。
このブームを牽引している存在として、カナダ発のブランド「ルルレモン(Lululemon)」が挙げられます。同ブランドは単なるスポーツウェアの枠を超え、質の高いライフスタイルを送る自立した女性の象徴としての地位を確立しました。
日本市場における戦略も特徴的で、単に知名度のある芸能人ではなく、プロのアスリートやヨガインストラクターをブランドアンバサダーに起用しています。
例えば、K-POPグループ「LE SSERAFIM」の日本人メンバーであるKazuhaさんを起用したことは、鍛え上げられた肉体とストイックな姿勢こそが現代の美しさであるというメッセージを強力に発信することとなりました。
また、世界的なアスレジャーの流行は、ありのままの自分の体型を肯定する「ボディポジティブ」の動きとも連動しています。ただし、これには議論がないわけではありません。創業者の過去の発言が物議を醸したこともありましたが、現在の消費者は、創業者の個人的見解と、製品の品質や現在のブランドが発信する「エンパワーメント(力づけ)された女性像」を切り離して評価している傾向が見られます。
欧米ではタイトなレギンスだけでなく、ややゆとりのあるシルエットへの回帰も見られますが、日本ではアジア人の体型に合わせた製品展開などにより、着こなしのハードルを下げる工夫が続けられています。
日本の街中で全身レギンスは定着する?
着用者たちの主張や世界的なトレンドの波がある一方で、日本社会全体で全身レギンスが完全に定着するには、まだ高いハードルが存在すると考えられます。
ある調査によると、日本人女性の約9割がレギンス一枚での外出に抵抗感を持っているとされており、日常的に着用している人であっても、スカートやショートパンツを重ね着(レイヤード)しているケースが多く見られます。
「自宅では良くても、街中では恥ずかしい」という心理は、日本特有の「恥の文化」や、周囲への配慮を重んじる公共マナーと深く結びついています。特に、下半身のラインが露わになることは、清潔感や慎み深さを大切にする日本の伝統的な価値観と衝突しやすいポイントと言えるでしょう。
こうした文化的な摩擦を和らげるために、日本独自の適応や進化も見られます。例えば、骨格に合わせてヒップラインをカバーするために長めのカーディガンを羽織るスタイリングや、股間のラインを目立たなくする「Yラインカバーインナー」といったニッチな解決策となる商品も登場しています。
これらは、トレンドを取り入れたいという欲求と、周囲から浮きたくないという心理の間で揺れ動く、日本市場ならではの「折衷案」と言えるかもしれません。
今後の展望として、全身レギンスが日本の保守的な文化をすぐに塗り替えるとは考えにくいものの、場所やシーンに応じた棲み分けが進むと予測されます。
ジムやランニングコース、空港などの「アクティブな非日常」の空間ではレギンス一枚履きが市民権を得る一方で、日常の街中や通勤・通学では、オーバーサイズのトップスと組み合わせるなどして露出を調整した「和製アスレジャー」として定着していく可能性があります。
若者たちの意識の変化は止まることなく、少しずつ日本の風景を変えていくことでしょう。
まとめ
全身レギンス姿に対する「見せたがり」という批判と、それに対する反論を分析すると、そこには単なるファッションの好みの違いを超えた、価値観の対立が浮かび上がります。
批判的な層がレギンスを下着に近い「隠すべきもの」と捉えるのに対し、着用する女性たちはそれを機能的なギア(装備)であり、自分の努力を肯定するためのツールと捉えています。
彼女たちの反論の核心は、「私の身体は誰かの視線のためにあるのではなく、私が活動するためにある」という、身体の主体性を取り戻そうとする強い意志にあると言えます。
彼女たちは、忙しい現代社会を効率的かつ快適に生き抜くための「戦闘服」としてレギンスを選んでいるのかもしれません。そこには欧米由来のボディポジティブの思想や、トレーニングによる自己研鑽の精神が混ざり合っています。
日本社会の保守性との摩擦は今後も続くことが予想されますが、アスレジャー市場の成長と新しい世代の台頭は、不可逆的な流れと言えるでしょう。
「見せたがり」という言葉で片付けるのではなく、彼女たちがそのスタイルを通じて表現しようとしている新しい時代の女性像や、他者の視線に縛られない生き方に目を向けることが、この現象を理解する鍵となるのではないでしょうか。
スポンサーリンク











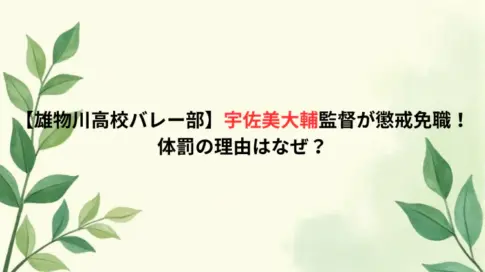

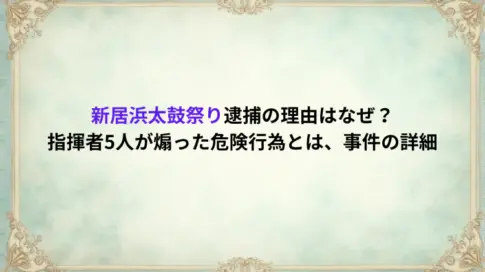












コメントを残す