スポンサーリンク
2024年、日本を訪れる外国人観光客の数は過去最高を記録し、その消費額も驚異的な水準に達しています。
しかし、この華々しい成功の裏で、「なぜ私たちの地域には、その恩恵が届かないのだろう?」と疑問を感じている地方の関係者は少なくないでしょう。
この記事では、「訪日客が増え続けているのに、なぜ地方は儲からないのか?」という多くの人が抱える根本的な問いに答えるため、最新のデータと専門家の分析を基に、その原因と具体的な解決策を深く掘り下げていきます。
この記事を最後まで読めば、地方が直面している課題の構造を理解し、明日から何をすべきかの具体的なアクションプランまで明確になるはずです。
訪日客が増え続けているのに地方の恩恵が少ない3つの根本原因

記録的な訪日客数を誇る一方で、その経済的な恩恵が一部の都市部に集中し、多くの地方へ行き渡っていないのが現状です。
この不均衡が生まれる背景には、大きく分けて3つの根深い原因が存在します。
原因1:訪日客の旅行先が「ゴールデンルート」に集中しているから
訪日客の恩恵が地方に行き渡らない最大の原因は、多くの旅行者が「ゴールデンルート」と呼ばれる特定の観光コースに集中してしまうことにあります。
ゴールデンルートとは、初めて日本を訪れる外国人観光客にとっての王道コースで、一般的に東京、箱根・富士山、京都、大阪を結ぶルートを指します。
このルートが絶大な人気を誇る理由は、まずその効率性にあります。ジャパン・レール・パスなどを利用すれば、新幹線で日本の現代的な大都市、雄大な自然、そして伝統的な古都という象徴的な魅力を短期間で体験できます。
さらに、このルート沿いには海外の旅行会社が企画するパッケージツアーや多言語対応のガイドブック、豊富な宿泊施設が集中しており、旅行者にとって「最も抵抗の少ない選択肢」となっているのです。
この一極集中は、都道府県別の外国人延べ宿泊者数のデータにも明確に表れています。東京都、大阪府、京都府の上位3都府だけで全国の外国人延べ宿泊者数の大半を占める一方、下位の県とは桁違いの差が生まれています。
例えば、トップの東京都が4,272万人泊を超えるのに対し、47位の島根県はわずか5.2万人泊と、その差は実に822倍にも達するのです。この構造が、地方に観光客の足が向かない根本的な理由となっています。
原因2:地方の魅力が外国人に知られていない・伝わっていないから
地方が持つ独自の魅力が、そもそも海外の旅行者に知られていない、あるいは十分に伝わっていないという「情報発信の課題」も深刻です。
地方創生のコンサルティングを行う永谷亜矢子さんは、多くの地域で観光客に情報が届いていない問題を指摘しています。
永谷亜矢子さんによると、デジタル上にターゲットが理解できる言語で情報が掲載されていなければ、それはターゲットにとって「存在していないのと同じ」です。
例えば、阿蘇市では魅力的な観光コンテンツがありながら、それを伝えるウェブサイトが分かりにくく、多くの機会を損失していました。
しかし、サイトを分かりやすくリニューアルしたところ、集客が5倍に向上したといいます。
この事例が示すように、どんなに素晴らしい観光資源があっても、その価値を伝え、旅行者が簡単に見つけられる情報発信の仕組みがなければ、訪れてもらうことはできません。多くの地方では、この情報発信の段階でつまずいているのです。
原因3:地方の受け入れ態勢がまだ十分に整っていないから
三つ目の原因は、地方における外国人観光客の「受け入れ態勢」が十分に整備されていない点です。これには交通、宿泊、そして「食」といった複数の側面が含まれます。
まず、主要な交通拠点から観光地までの「ラストマイル」と呼ばれる二次交通の脆弱性が大きな障壁です。地方のバスや鉄道は運行本数が少なく、乗り継ぎも不便なため、旅行者は柔軟な旅程を組むことができません。
次に、宿泊施設の不足も深刻です。多くの地方では、急増するインバウンド需要に対応できるだけの客室数が確保できておらず、多様な旅行者のニーズに応えられる宿泊施設の選択肢も限られています。
さらに、フードダイバーシティ株式会社は、特に「食」に関する対応の遅れを指摘しています。ハラール対応など、食の多様性に応える飲食店の数は都市部に集中しており、地方では極端に少ないのが現状です。
訪日客が地域ならではの食を求めて地方へ足を運んでも、「食べられるものがなかった」という事態が起きてしまえば、再訪には繋がりません。これらの受け入れ態勢の不備が、地方への訪問をためらわせる大きな要因となっているのです。
そもそも訪日観光客はなぜこれほど増えたのか?最新の理由を解説

地方への恩恵という課題を考える前に、まずはなぜ今、これほどまでに多くの外国人観光客が日本を訪れているのか、その背景にある理由を理解しておくことが重要です。
最大の要因は「歴史的な円安」で日本旅行が格安になっているから
現在のインバウンド市場の活況を支える最も強力な追い風は、歴史的な円安です。海外の旅行者にとって、日本の商品やサービスが非常に割安に感じられるため、旅行先としての魅力が格段に高まっています。
この円安を背景に、旅行者一人当たりの支出額も増加傾向にあり、滞在日数が長期化する傾向も見られます。この「お得感」が、訪日客数を押し上げる最大の原動力となっています。
ビザ緩和や免税制度など日本政府の観光戦略が後押し
コロナ禍後の水際対策緩和が、訪日客急増の直接的な引き金となりました。入国制限がなくなったことで、堰を切ったように旅行者が日本に戻ってきました。
また、日本政府は以前から「観光立国」を掲げ、2030年までに訪日外客数6,000万人、インバウンド消費額15兆円という野心的な目標を掲げています。
ビザの緩和や免税制度の拡充といった一連の政策が、日本への旅行のハードルを下げ、市場の成長を後押ししているのです。
アニメ・日本食・伝統文化など「本物の日本」を体験したい人が増えた
旅行者の価値観の変化も、訪日客増加の大きな要因です。かつての「爆買い」に代表されるような、物を買う「モノ消費」から、その土地ならではの体験や文化に触れる「コト消費」へと、消費の重心が明確に移行しています。
アニメや日本食、伝統的な祭り、手つかずの自然といった、大都市では味わえない「本物」の日本を体験したいというニーズが高まっており、これが日本の多様な魅力への関心を引きつけています。
「日本は何度来ても楽しい」リピーター客の存在も大きい
日本を一度訪れた旅行者が、その魅力に惹かれて再び訪れる「リピーター」の存在も市場を支える重要な要素です。
リピーターは、一度目の旅行で東京や京都といった主要な観光地を訪れた後、二度目以降はより深く、まだ知らない日本の魅力を求めて地方へ足を運ぶ傾向があります。
彼らが「コト消費」を牽引し、地方観光の新たな可能性を切り拓く存在となっているのです。
スポンサーリンク
【データで見る】外国人観光客は日本のどこを訪れている?

訪日客が日本のどこに魅力を感じ、実際にどこを訪れているのかをデータで見ていくと、都市部への集中と地方が持つポテンシャルの両方が見えてきます。
やはり人気?都道府県別の訪問率ランキングTOP10
外国人延べ宿泊者数のデータを見ると、やはり人気は都市部に集中していることが分かります。2023年のデータに基づくと、ランキングの上位は以下のようになっています。
1位は東京都(約4,272万人泊)、2位は大阪府(約1,848万人泊)、3位は京都府(約1,211万人泊)と、この3都府で圧倒的な数を占めています。
続いて4位に北海道、5位に福岡県、6位に沖縄県、7位に千葉県、8位に神奈川県、9位に愛知県、10位に長野県が入っており、ゴールデンルートとその周辺、そして独自のブランドを確立した一部の地域に人気が偏っている実態が浮き彫りになります。
意外な結果?訪問者数の伸び率が高い地方エリアはどこか
コロナ禍後の回復期において、この格差は縮小するどころか、むしろ拡大する傾向にあります。2024年のデータによれば、三大都市圏における外国人延べ宿泊者数は前年比で約5割増と急増しているのに対し、地方部では約2割増に留まっています。
これは、新たな観光需要が、既に混雑している都市部へさらに流入していることを示しており、地方との差が能動的に再生産されているという厳しい現実を物語っています。
このデータは、対策を講じなければ格差が自然には埋まらないことを示唆しています。
外国人は日本の何に魅力を感じているのか?最新アンケート結果
では、外国人は日本の何に魅力を感じているのでしょうか。
米国の旅行雑誌『コンデナスト・トラベラー』が「世界で最も魅力的な国」ランキングで日本を1位に選んだように、日本の魅力は国際的に高く評価されています。
その魅力の源泉は、近年ますます重要視されている「コト消費」、つまり体験価値にあります。
具体的には、手つかずの美しい自然や四季折々の風景、登山やラフティングといったアウトドア活動、伝統的な旅館での宿泊や祭りへの参加、そして地元の食材を活かした郷土料理や温泉(おんせん)といった、その土地でしか味わえない本物の体験が、多くの外国人観光客を惹きつけているのです。
なぜ訪日客の都市部集中は問題なの?オーバーツーリズムの深刻なデメリット

一部の都市に観光客が集中することは、地方が恩恵を受けられないだけでなく、集中する都市部そのものにも深刻な問題を引き起こします。それが「オーバーツーリズム」です。
オーバーツーリズムとは?その意味と起こる原因をわかりやすく解説
オーバーツーリズムとは、特定の観光地にあまりにも多くの観光客が訪れることで、地域住民の生活や自然環境、さらには観光客自身の満足度にまで悪影響が及んでしまう状態を指します。
日本語では「観光公害」とも呼ばれます。その主な原因は、本記事で繰り返し指摘してきた通り、特定の人気観光地、特にゴールデンルートのような場所に観光客が過度に集中してしまうことです。
交通機関の麻痺やゴミ問題など地域住民の生活への影響
オーバーツーリズムが深刻化すると、地域住民の日常生活に様々な支障が生じます。例えば、バスや電車が観光客で満員になり、地域住民が利用できなくなる交通機関の麻痺。観光客が捨てるゴミの処理が追いつかなくなるゴミ問題。
そして、静かな住宅街にまで観光客が押し寄せ、騒音問題が発生するなど、生活環境が悪化するケースが京都や鎌倉などの人気観光地で実際に報告されています。
観光客の満足度低下という悪循環も
オーバーツーリズムは、地域住民だけでなく、訪れている観光客自身の満足度をも低下させるという悪循環を生み出します。どこへ行っても混雑し、長時間待たされ、ゆっくりと観光することができない。
このような体験は、旅行の質を著しく損ないます。「せっかく来たのにがっかりした」というネガティブな評判が広がれば、その観光地の長期的なブランド価値を傷つけることにもなりかねません。
【成功事例に学ぶ】訪日客を地方に呼び込むためのヒント

都市部への一極集中という厳しい現実がある一方で、独自の戦略で多くの外国人観光客を惹きつけ、成功を収めている地方も存在します。彼らの取り組みから、地方誘客のヒントを学びましょう。
【事例紹介】独自の魅力で外国人を惹きつける日本の地方エリア3選
1. 高山市(岐阜県):30年越しの統合戦略
岐阜県の山間部に位置する高山市は、30年以上前から「国際観光都市」を掲げ、官民一体で一貫した戦略を推進してきた地方インバウンドの先駆者です。東京と京都の間に位置する地理的特性を活かし、自らをゴールデンルートの経由地として位置づけました。早くから多言語対応や無料Wi-Fiの整備に力を入れ、近隣の世界遺産・白川郷と連携した周遊ルートを開発するなど、旅行者の利便性を徹底的に追求することで成功を収めています。
2. ニセコエリア(北海道):富裕層ニッチ戦略
北海道のニセコエリアは、「世界屈指のパウダースノー」という唯一無二の資産に資源を集中させ、世界的なスノーリゾートとしての地位を確立しました。英語が公用語のように使われる環境を整備し、積極的に海外からの投資を呼び込むことで高級リゾート地へと変貌。冬季だけでなく、夏季のアクティビティも開発し、通年型リゾートとして安定した経済基盤を築いています。
3. せとうちDMO(瀬戸内7県):広域ブランディング戦略
瀬戸内海を囲む7県が連携する「せとうちDMO」は、個々の県の枠を超え、「せとうち」という統一ブランドを構築することで成功しました。アートやサイクリングといった地域横断的なテーマを掲げ、7県が持つ資金やノウハウを集中させることで、単独の県では不可能な大規模なマーケティングを展開。世界に通用する魅力的なデスティネーションイメージを創り上げています。
成功事例に共通する「体験価値」と「情報発信」の戦略とは
これらの成功事例には、重要な共通点が見られます。それは、その地域ならではの「体験価値(コト消費)」を磨き上げ、それをターゲットに的確に届ける「情報発信」に長けている点です。
高山は「日本の田舎」、ニセコは「最高の雪質」、せとうちは「アートと自然」という、他にはない独自の価値を明確に打ち出しています。
そして、その価値を伝えるために、多言語対応のウェブサイトやデジタルインフラの整備といった「ソフト」面の充実に粘り強く取り組んできました。
専門家である永谷亜矢子さんが指摘する「編集力」、つまり地域の魅力を分かりやすく伝え、ウェブサイトなどを通じて世界に発信する力が、成功の鍵となっているのです。
私たちの地方でもできる!明日から始めるインバウンド誘致アクションプラン

成功事例は遠い世界の出来事ではありません。彼らの戦略から学び、自分たちの地域で実践できることは数多くあります。
ここでは、明日から始められる具体的なアクションプランを提案します。
まずは地域の「隠れた魅力」を外国人目線で再発見する方法
インバウンド誘致の第一歩は、自分たちの地域の魅力を再発見することから始まります。専門家の永谷亜矢子さんが言うように、地元の人々が「なぜこんなに大変なことを何百年も続けているのだろう」と思うような伝統的な祭りや風習こそが、外国人にとっては非常に価値のある観光資源になり得ます。
当たり前だと思っている風景や食文化、人々の暮らしの中にこそ、「本物」の魅力が眠っています。まずは外部の専門家や地域外の人の意見も取り入れながら、外国人目線で地域の資産を洗い出してみましょう。
SNSや海外向けメディアを効果的に活用した情報発信術
地域の魅力を見つけたら、次はその情報を世界に届ける番です。現代の旅行者の多くは、SNSやウェブサイトで情報収集を行います。
まずは、自分たちの地域の魅力をターゲットが理解できる言語で発信する公式なウェブサイトを整備することが不可欠です。サイトはただ作るだけでなく、予約までスムーズに行える分かりやすい設計が求められます。
さらに、地域の「コト」に魅力を感じるであろう特定の国の旅行者が利用するSNSプラットフォームで、的を絞った情報発信を行うことや、海外のインフルエンサーと連携することも有効な手段です。
多言語対応・キャッシュレス決済など最低限必要な受け入れ環境の整備
情報発信と並行して、訪れた観光客がストレスなく過ごせる環境を整えることも急務です。駅やバス停の案内表示、飲食店のメニューなどを多言語対応にすることは基本中の基本です。
また、無料で安定した公衆Wi-Fiの整備や、クレジットカード、電子マネーといったキャッシュレス決済への対応は、現代の旅行者にとって必須のインフラです。
さらに、フードダイバーシティ株式会社が指摘するように、ハラール対応メニューを1品でも用意するといった食の多様性への配慮も、選ばれる地域になるための重要な一歩となります。
まとめ:地方の未来はインバウンド戦略が鍵|可能性は無限大

日本のインバウンド観光が記録的な成長を遂げる今、その恩恵を地方にいかにして波及させるかが、国全体の持続可能な発展の鍵を握っています。
訪日客の地方分散は日本全体の持続可能な観光につながる
観光客を都市部から地方へ分散させることは、オーバーツーリズムという都市問題を緩和すると同時に、地方に新たな経済の柱をもたらします。
これは、日本が持つ魅力の多様性を世界に示し、一部の地域に依存しない、よりバランスの取れた観光国家を築くことにつながります。
日本のインバウンド観光の未来は、多様で魅力的な地方のブランド体験から成る「ポートフォリオ」をいかに構築できるかにかかっているのです。
「何もない」ではなく「まだ知られていないだけ」という視点を持とう
「うちの地域には何もないから」と諦める必要は全くありません。フードダイバーシティ株式会社が指摘するように、観光客が来ないのは「自ら選ばれないようにしているから」かもしれません。
成功事例が示すように、どんな地域にも必ず独自の魅力があります。重要なのは、「何もない」という思い込みを捨て、「まだ知られていないだけ」「まだ伝わっていないだけ」という視点を持つことです。
その隠れた宝物を発見し、磨き上げ、世界に向けて発信する。その一歩を踏み出すことで、あなたの地域の未来は大きく変わる可能性を秘めています。
参考情報
免責事項
本記事は、情報の正確性や完全性を保証するものではありません。また、本記事の内容は特定の投資や行動を推奨するものではなく、最終的な判断はご自身の責任において行ってください。本記事の情報を利用した結果生じたいかなる損害についても、作成者は一切の責任を負いません。
スポンサーリンク









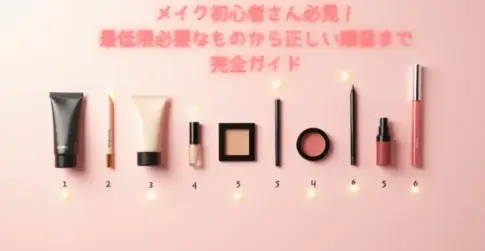



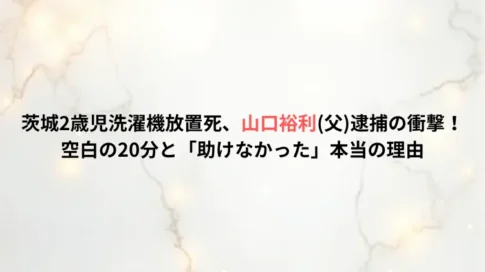
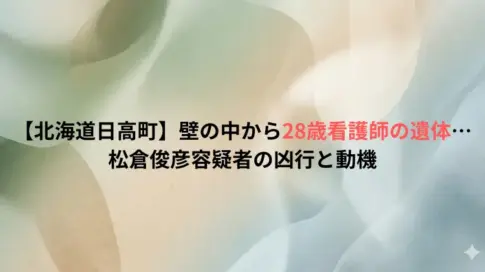








コメントを残す